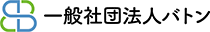ーー菓子博開催の効果を、どう予想していますか。
水上 全国で菓子博があるたびに、私たちも業界で30人くらいのツアーを組んで訪問していました。菓子博を見学してから、老舗のお菓子屋さんを回り、観光も楽しんで3~4泊で帰ってくるパターンでした。北海道の中心に位置するのが旭川ですし、周辺の観光や自然体験、グルメなどを考えると、北海道への経済効果や食の優位性を全国に発信する絶好の機会だと捉えています。旭川は、まだまだ魅力を発信できていません。伝えきれていない部分を、菓子博をきっかけに発信していければと思います。経済波及効果は、約31・6億円になるとみています。
ーー展示の内容を教えてください。
水上 大きくは、3つのメインコンテンツがあります。一つは、菓子職人(菓匠)が、伝統の技術でつくる工芸菓子の展示です。約90作品が出品され、審査を経て名誉総裁賞、内閣総理大臣賞、農林水産大臣賞などの賞を決めます。一般に販売されているお菓子は、約1200商品が集まります。こちらも審査を経て、同じように賞を決めます。全国のお菓子屋さんが、賞を取りたくて出品します。賞を取った300弱くらいの商品が、会場でも展示、販売されます。もう一つは、普段買えない全国のお菓子が揃う「全国スイーツマーケット」で、ここでは、1000品以上が販売されます。
菓子博のシンボル展示として、これまでは、姫路の場合なら姫路城、伊勢では、お伊勢参りの風景などを工芸菓子でつくって展示をしていました。これは、審査対象ではなくて、開催地の菓匠たちが、力を合わせて制作する、文字通りシンボルと位置付けられていました。北海道の場合、菓匠が少ないことに加え、菓子博が終わったら、こうしたシンボル展示品は廃棄されてしまうので、SDGsの時代にはそぐわないとして、北海道のお菓子の魅力と菓子材料の宝庫という、2つのコンテンツを融合させたプロジェクションマッピングを、シンボル展示に置き換えることにしました。
会場となる道北アークス大雪アリーナ内に、大きなドームを設営して、そのドームに映像を投影します。過去になかったようなお菓子の世界を映像化します。田植え、麦植えから始まって、芽が出て収穫するまでの光景を昨年、8Kの映像で撮っています。そこから、原材料ができるところや加工されたもの、例えば、生クリームの中に自分が入っていってしまうような映像体験を提供します。基本は、5分間のバージョンですが、土日の混雑時は、3分バージョンも投影します。
先ほどの約90作品の工芸菓子の中で、道内では、函館の「吉田食品」さんや北見の「大丸」さん、帯広の「柳月」さんなどが、大型のものを出品します。地元からは、今回、「壺屋総本店」さんがチャレンジします。洋菓子の工芸菓子も出品されるので、道内の出品数は、15以上になります。また、毎回、菓子博では、全国の大手7~8社がパビリオンをつくって、ペコちゃんなど着ぐるみが登場して、子どもたちを楽しませてくれる体験型イベントを行っています。今回は「スイーツファミリーランド北海道」と名付けて、大手7社(ブルボン、森永、明治、ロッテ、カルビー、不二家、山崎製パン)がパビリオンを出します。
ーー北海道ならでは、旭川ならではの展示はありますか。
水上 北海道は、お菓子の原材料の宝庫です。小麦、乳製品、バター、もち米、それらを大きくアピールしてお菓子に繋げるのが、今回のサブテーマです。これは、他の地域では、できない取り組みです。販売ブースでは、北海道のブースを大きく取って、旭川のお菓子や北海道のお菓子をたくさん並べます。また、北海道の原材料を使って、お菓子づくりの実演、販売も大規模に行います。
――今回の菓子博の予算規模は。
水上 全体では5億円を予定しており、これまでの菓子博に比べて、3分の1~4分の1のコンパクト化を実現します。入場者数は、過去の菓子博では60万人程度でしたが、20万人くらいになるとみています。しかし、コンテンツ的には半分にもなっていないので、かなり見どころはあるでしょう。
ーークラウドファンディングも行っていますね。
水上 会場には、ドームを2つ設営しますが、小さなドームでは、使い終わったお菓子の包装紙で折った鶴を展示します。鶴は、全国から送ってもらったものを使います。鶴の展示によって、お菓子を食べたりつくったりできるのは、平和で幸せなことだとアピールします。災害とか紛争があると、お菓子をつくることも食べることもできません。平和の象徴の鶴に、その想いを託そうというわけです。クラウドファンディングで集めたお金は、この鶴を展示するための費用やLED照明の経費として使います。返礼として、金額に合わせてお菓子のセットが贈られるほか、大会会場で、優先して見学できるファストパスを交付します。目標は300万円です。