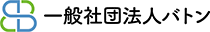和菓子を中心に、洋菓子・スナック菓子なども含めた日本最大級のお菓子の祭典「第28回全国菓子大博覧会・北海道あさひかわ菓子博2025」が、2025年5月30日(金)から始まる。ほぼ4年に1回、全国で開催されてきた菓子博だが、コロナ禍の影響などで開催地がなかなか決まらず、前回の伊勢市から8年ぶりの開催となる。北海道での開催は、57年ぶり。今回の菓子博から、会期を17日間(同年6月15日まで)に短縮、経費面でもコンパクト化を進め、新たな時代に対応した菓子博として開催される。「あさひかわ菓子博」実行委員長で、北海道のかりんとう屋「北かり」で知られる三葉製菓代表取締役の水上崇さんに、菓子博の狙いと効果などを聞いた。 (写真は、インタビューに応えるあさひかわ菓子博実行委員長の水上崇・三葉製菓代表取締役)
(写真は、インタビューに応えるあさひかわ菓子博実行委員長の水上崇・三葉製菓代表取締役)
ーー第28回全国菓子大博覧会の開催地が、旭川に決まるまでの経緯を教えてください。
水上 菓子博は、100年以上前の1911年から、おおよそ4年に1回、開催されてきました。今回は、28回目になりますが、27回の伊勢開催までは、大規模なイベントになりすぎていました。伊勢の前が広島、その前が姫路です。姫路では、有料入場者が90数万人でしたが、小学生を無料にしたので、実質的には100万人を超え、開催経費も25億円だったと聞いています。いずれの開催地でも県や市、近隣町村が、開催経費をバックアップしてきた経過があります。
毎回、次の開催地を決めてから閉幕していたのですが、伊勢の次の開催地が決まらないまま終わりました。その理由に、コロナの感染拡大があったこともありますが、行政の負担が大きい上、お菓子の大企業が少ない地域では、経費面から開催が難しくなっていたからです。菓子博は、西日本での開催が続いていました。1998年に盛岡市で開催したり、もっと前の1968年には、札幌で開催したりしたことがありましたが、2002年以降は、西日本での開催でした。そんなことから、業界内には、「次は、北日本、東日本で」という声が多くなっていたのは、事実です。
そうした中、北海道菓子工業組合の理事長(全国菓子工業組合連合会副理事長)を務めている、きのとや会長・長沼昭夫さんが、「なんとか北海道で開催できないか」と、地元の菓子工業組合に打診され、「札幌で」ということになりかけました。ところが、札幌では、長期間使用できる会場がなかなか押さえられないことや、国際都市として知名度もあることから、「函館、帯広、旭川、北見で開催できないか」ということになりました。それで、旭川JCの理事長を務めていた、私を含めた旭川のお菓子屋さんのトップが、就任早々の今津寛介市長に開催を持ち掛けました。市長もJC理事長を経験しており、「よしやろう」ということになり、「開催するなら、これまでと違うコンパクトな大会にしよう」ということで、北海道菓子工業組合の理事会で正式決定しました。大会期間は、1週間短くして、24日間から17日間にすることなどが決まりました。57年ぶりの北海道開催になります。
ーー旭川には、お菓子づくりの歴史があって、技術の蓄積もあります。
水上 旭川は、言うまでもなく、軍都として発展した街です。戦前は、第七師団があって、今は、買物公園通りと呼ばれていますが、当時は『師団通り』と呼ばれていて、駅前からロータリーを通って旭橋までの通り沿いには、お菓子屋さんがたくさんありました。今も営業している「まるきた」さんや「きたぐち」さんがありますし、「壺屋総本店」さんの本店や「梅屋」さんも、あの通り沿いにありました。歴史的に見ても、この地域には、お菓子の原材料となる小豆やもち米が豊富にありました。そうした恵まれた環境の上に、軍都の需要にも支えられて、お菓子づくりが発展してきた経緯があります。こうした歴史に裏打ちされた旭川で菓子博を開催することによって、旭川のみならず、北海道のお菓子が、全国に発信できれば良いと思います。