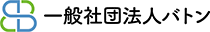ーーケーキの宅配で事業の基盤ができたということですか。
長沼 バースデーケーキなどデコレーションケーキを中心に、店頭売りに宅配を加えながら広く販売しました。全国には、たくさんケーキ屋さんがありますが、その中でも当時の「きのとや」は稀な存在でした。宅配自体が稀だったし、そもそもそういうケーキ屋さんはどこにもなかった。「白石店」の売り上げは年間11億4000万円にもなり、単店で日本一になったこともあります。ケーキ専門店としては、圧倒的に日本一でした。
その頃に、基盤ができましたが、その後、食中毒事故を起こしてしまいました。周りを見ると、商売が順調なお菓子屋さんは、大半がお土産菓子を作っています。お菓子業界は、お土産菓子がなければだめなんだということや、日持ちのするお菓子を作って大量に販売しないとやっていけないと感じました。「札幌農学校」が生まれる前に、半生菓子のチーズスフレを当時の千歳空港でお土産菓子的に売り始めましたが、要冷蔵だからなかなか売れなかった。常温保存で日持ちのするクッキーを志向して、「札幌農学校」が生まれました。
ーーヒット商品を作り続けられているのは、なぜですか。
長沼 私が、作り手ではないことが大きいのではないか。普通のお菓子屋さんは、オーナーパティシエが多く、自分で作って、自分が経営者になっています。しかし、それでは限界があると思います。私は自分で作らないので、幅広くさまざまな情報を入手しながら、「こんなお菓子だったらうちに向いているのではないか」、「こんなお菓子ができたらいいね」と、そういう目線でお菓子を見ます。現在のきのとやなど、北海道コンフェクトグループの強みは、まさにその商品開発部門ですし、この部門は今も強化しています。パティシエは7~8人いますし、企画担当も3~4人います。その人たちに、課題をどんどん与えていくのが、私や息子(長沼真太郎・北海道コンフェクトグループ代表取締役)の役目です。彼らが、一生懸命考えて作ってきたものに対して、「ダメ」と言わなければならない場合もあります。それが当社グループの命なので、妥協はできない。どんどん“ダメ出し”するので、彼らの心が折れる時もあると思います。
今、千秋庵製菓を含めて北海道コンフェクトグループという、お菓子の幅を広げたグループをつくることができているのも、私自身がパティシエでも職人でもなかったからです。そのことは、すごく感じます。
ーー新しい菓子のヒントを得るためには、いろいろな情報が必要になります。
長沼 以前は、実際に自分の足で見て歩かないと分かりませんでしたが、今はそれが必要ではなくなった。すべてネットで簡単に情報が入ってくる時代です。私はネットを駆使している方ではありませんが、若い人たちはそういうところからいろいろと情報を集めて、ヒントにしているようです。私がお菓子屋を始めた頃は、とにかく自分たちで見に行かないと新しい発見がありませんでしたから、海外を含めて始終出かけていました。でも、今は、そういう必要がない。日本語の検索では出てこなくても、英語で検索すると、すごい情報量が出てくるそうです。私はできませんが、息子たちは、そうやって世界から情報を集めてヒントを得ているようです。
ーーそれらの情報を汲み上げて、「きのとや」らしい商品を作り上げていくには、経験も必要です。
長沼 息子たちがアイデアを出して、開発メンバーたちが試作したものを、私が食べて、『これはだめ、甘すぎる、構成が悪い』などと判断します。商品化の判断をする役割と言えばいいでしょうか。
ーー40周年記念の菓子として「風の音」をラインナップされました。
長沼 「風の音」というネーミングは、彫刻家の五十嵐威暢先生が、「白石本店」に作ってくれた大きなレリーフから引用しています。記念菓ができるまでに二転三転して、もう少し風になびく形を考えていましたが、そうもいかなくて、あの形になりました。開発までに1年以上はかかっていますが、食べて美味しい記念菓に仕上がりました。おししくないと、どんなにアイデアが良くても2回目は買ってくれません。誰かにあげたくなるようなものでなければ、売れないものです。
ーー今も、舌、味覚には自信があると。
長沼 いや、もう自信ないですよ。「私の舌はあてにならんぞ」と言っているのですけどね。若い人たちが、自分たちの感覚で商品を作っていかないと時代に取り残されてしまいます。そろそろ、当社グループも世代交代するでしょう。私は、なるべく早くお菓子作りから牧場作りに専念したいと思っています(笑)。