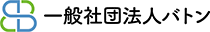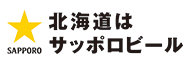ーー函館インクルージョン未来アンバサダーを委嘱するなどインクルージョン推進を打ち出されています。
大泉 ともすると、障害を持っている方、高齢の方、困難を抱えている方をどうケアするか、ということだけに話がフォーカスしてしまいます。もちろん、それは大事なことなので、地方公共団体の当然のミッションとして行いますが、障害のある人とない人という分断の意識を地域が持ってしまうのは不幸なことです。インクルージョンがフォーカスするのは、困難を抱えている人の周りにリーチすることです。
個人、個人が輝きや尊厳を持っています。そこには何の違いもないし、隔たりも壁もありません。皆で一緒に働いたり、喜んだり、楽しんだり、学んだりできる場を持つべきであって、障害のあるなしや年齢、性別、国籍も関係ないインクルージョンが実現できる社会にすべきだろうと。
これは、実は定義があってないようなものです。インクルージョンって何だろうっていうのは、今まさに皆で考えていく段階だと思うし、私たち市役所が定義を決めるものでもありません。インクルージョンって何だっていうことを、問い続ける始まりが、今ということです。
そもそも、役所の仕事と言えば、例えば目に見えるインフラ整備、そして子育て、高齢者支援など、制度の充実が思い浮かびます。これは当然、必要です。人間に例えれば身体みたいなもの。身体は絶対必要で、身体が整えば「優れた街」になれると思う。だけど、優れた街だけでは、今の急激な人口減少は止められません。「卓越した街」でないと、今の危機は突破できないと思っています。卓越した街というのは、体だけではなくて、その真ん中に“心”というか、考え方の“芯”がないといけないと思います。インクルージョンは、その重要な一つだろうと思っています。それを街全体で共有できるようになった時に、函館は、卓越した街になれるのではないかと思っています。
ーーひきこもり問題について、市長は部長時代からこの問題に見識、造詣を深めて取り組んでこられた。
大泉 これこそ一朝一夕でできるものでは、ありません。例えば、何か制度をつくって、どこかの事業者に窓口をつくってもらったり、支援機関を強化したりするようなことを一律でやっても、対応できないと思います。きめ細かくサポートしたいというようなプレーヤーが現れてこないと、物事は進まないと思います。ここにも時間がかかります。
何より、ご本人やご家族自身が、心の活力のようなものを失いつつある、あるいは失ってしまっている時、支援しようにもアプローチしようにも難しかったりします。皆が支援のスキルを上げていくようなことも含めて行っていかなければならないと思います。
大事なのは、選択肢があること。どうしたらいいのか、どうしようもない、というところに追い込まれていく手前で、こういう選択肢もある、別の選択肢もあるという選べる環境があることが大事だと思います。
市は、道南ひきこもり研究会「あさがお」など、当事者のご家族の会とも連携しています。不登校・発達障害を考える保護者会「函館アカシヤ会」には、昨年の夏に市民貢献賞を贈呈しました。最近「函館アカシヤ会」では、「リンクアップ」という当事者の集まりができて、若い人たちで始めたばかりですが、私は、その会合に時折り勉強のために参加しています。これは公務ではなくて、顔を出すという感じで出席して話をしています。
ーー公務を離れて、大泉潤氏個人として参加されていると。
大泉 「暑いね」から始まるような感じです。首長としてではないし、コーディネーターみたいなことができるタイプでもないので、僕は黙って聞いて、喋りたくなったら喋るという具合です。
ーー1期目は残り2年です。街の小さな声を聞く重要性をより感じている、と。
大泉 市役所に入ってから30年以上が経ちますが、基礎自治体で働きたかったというのが、市役所に入った理由です。直接、住民と会って話をするーーそれをヒントに、少しでも社会が変わるような制度改変をするのが、基礎自治体のミッションでもあり、強みでもある。それが、私の原点です。市民の声を聞くというのは、別に何か変わったことをしているわけではありません。必要なことを、これからも当たり前にやり続けていきたいと思います。
――本日はありがとうございました。