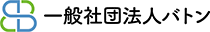(写真は、左から福山耕司社長、福山誠司専務)
(写真は、左から福山耕司社長、福山誠司専務)
――企業としての取り組みが、多岐にわたります。
福山 そうですね。ここ数年の取り組みでいくと、食品安全の国際規格である「FSSC22000」を取得しました。品質のさらなる向上や、海外取引の拡大をにらんだものですが、社会貢献という観点で言えば、社会福祉法人との連携や工場見学、味噌作りの場を提供する食育活動を実施しています。工場見学には、年間3000人を超える方々にお越しいただいていますし、食育のイベントには、幅広い年代の方々にご参加いただいています。
食育イベントの概要に触れると、親子で楽しむという内容だけでなく、大人も楽しめるという視点も大切にしています。日本の多くの家庭には、味噌・醤油は、当たり前にあるのかもしれません。でも、知らないことは多いものです。イベントを通じて、食に興味を持ち、日常にある当たり前のモノの価値に気づいていただけたらありがたいですね。
加えて、保護猫活動も企業として応援しています。保護猫団体と提携して商品開発を行い、その商品の売り上げの一部を保護猫活動に役立てていただくというものです。女性社員が保護猫団体と接点を持ったのがきっかけですが、今では『ネコんぶしょうゆ』など、猫関連の商品も多く展開しています。社員の多くが猫好きだから、この企画はトントン拍子に進みましたね。(社長も猫好きですか?)もちろんだよ(笑)。
――社員教育、人材育成については。
福山 新入社員に対しては、自社で作成する教育・訓練計画を実践してもらっています。主に自社商品や他社商品を学ぶというものですが、味噌・醤油は極めて奥が深い。ベテラン社員も日々研修を重ね、新たな発見を繰り返しているところです。資格で言えば、北海道フードマイスター、味噌ソムリエ、味噌技能士、総菜管理士など、職種に応じた資格を社員が取得しやすいよう会社がバックアップしています。
また、これからは営業と製造のスタッフが、セットでお取引先にうかがう仕組みを強化していく必要があると感じています。「メーカーとしてできることを追求する」、こういった観点からです。
――未来に向けて、企業としての投資は。
福山 事業すべてが投資だと思っています。「トモエ」の姉妹ブランドとして立ち上げた「ヤマト福山商店」も投資、開発を進める麹の商品も投資です。突き詰めれば、明日以降のことは、全て投資と捉えています。
――将来的な商品開発について。
福山 時代が進むにつれライフスタイルも多様化を極めています。ですが、常に潜在的なニーズが眠っています。これをいち早く読み取り、当社の強みを生かした、“ならでは”の多様な商品を展開していく必要があります。北海道のメーカーである以上、北海道のおいしい素材を生かした商品作り、生活の中になじむ商品作り、さらには、道民の健康を意識した商品、タイムパフォーマンスに優れた商品に、一層磨きをかけることにも尽力しなければなりません。
願わくは、「トモエ」と「ヤマト福山商店」が、世界に広がる北海道ブランドの一翼を担えればと思っています。また、我々が展開する商品は、全て食べ飽きしないものばかりです。おいしいが、3日で飽きるような商品ではあってはならない。だからこそ、自然に近い味を追求する必要があるわけです。調味料は主役ではありません。素材を引き立てる脇役です。必要以上に味に特徴をつけたり、パンチを持たせようとしがちですが、それでは素材の味が損なわれてしまいます。あくまで主役を立てるのが調味料。でもたまには、脇役が主役以上に活躍する――、そんなこともありえますけどね(笑)。
――創業134となりますが、150年、200年にはどういったビジョンを描いていますか。
福山 創業は明治です。現代とは比べ物にならないほど、何もない時代だったことは想像に難くない。創業者はそうした中で、事業をスタートさせた。チャレンジすることが目の前にあったからでしょう。やはり、どの時代もチャレンジするというマインドが肝心です。もちろん歴史は貴重な財産ですが、過去は過去。必要以上にこだわらずに、今できること、求められることに全力で取り組むだけです。