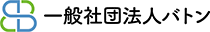130年以上にわたり、北海道の食卓を支え続ける福山醸造(本社・札幌市東区)。1891年創業の老舗で、これまで数えきれない商品を世に送り出してきた。伝統を守りつつも、次世代に求められる商品の開発にかける想いは強く、近年では、“麹”を活用した商品が話題に。人口減少、物価高騰と、苦境を迎える業界で成長し続ける要因を福山耕司社長にインタビューした。 〈ふくやま こうじ〉1952年生まれ。玉川学園大卒。1978年福山醸造入社、2001年代表取締役就任。一度退任し、2021から再就任。ギターやサックス、ウクレレなど、中学から続ける音楽(ジャズ)と、車をこよなく愛す。
〈ふくやま こうじ〉1952年生まれ。玉川学園大卒。1978年福山醸造入社、2001年代表取締役就任。一度退任し、2021から再就任。ギターやサックス、ウクレレなど、中学から続ける音楽(ジャズ)と、車をこよなく愛す。
――商品展開が多岐にわたります。とりわけ近年は、“麹”を使用したコーヒーや美容関連商品が話題を呼んでいますが、どのようなスタンスで新商品の開発を?
福山 新たな商品の開発は常に行っています。ですが、ベースにあるのは、やはり弊社の両翼である味噌・醤油。ここは決してブレていません。自社の強みを、従来の枠に捉われずに追求した結果が、麹の可能性だったということです。麹の魅力は幅広く、日本人の食文化と麹は、切っても切り離せません。アジアにも似た発酵文化はありますが、“米麹”は日本独自の存在です。弊社では教育機関と連携し、まだ解明されていない麹の機能性について研究を続けています。食卓に限らず、さまざまな場面で麹が活用される日も近いでしょう。
――創業134年となる中で、変わらないものもあると思います。
福山 味噌、醤油の基本的な製法ですね。もっとも、衛生管理などについては常にアップデートしていますし、設備もサービス向上を図るために必要なものであれば更新しなければならない。ただ、製法に関しては変えるつもりはありませんし、原材料に道産品を使用することについても変えるつもりはありません。“地産地消”、ここはこの先もこだわっていきたいですね。
――若年層の“味噌離れ”については、どうですか。
福山 人口減少が進み、食文化、ライフスタイルが大きく変化する中で、家庭内調理器具・器材の販売数も減少していると聞きますから、そういった見方をされるのも理解できなくはありません。 ただ、世界的に見れば、味噌や醤油の価値は、年々高まりを見せている。増加傾向にある輸出量がその証拠です。
こうした背景があるにもかかわらず、我々のようなメーカーが事業の多角化に取り組むと、味噌や醤油の先行きを懸念しての展開と見られがちですが、これは適切ではない。我々を例にすると、麹の可能性を追求した結果なわけです。とはいえ、これまでと同じことを繰り返してばかりいては、発展がないことも確か。伝統を紡ぎつつ、新しいことに挑戦し、必要な存在としてあり続けていくことを意識していきたいですね。
――昨今の高騰するエネルギーコストについて。
福山 エネルギーコストの削減については、常に注視しています。生産コスト、固定費の改善についても同様です。ですが、品質は絶対に下げるわけにはいかない。品質を担保しながら、業務、コストを見直す経営努力は永遠の課題です。