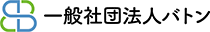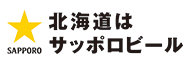日本アクセス北海道(本社・札幌市東区)は、北海道No.1食品卸企業を目指した第8次中期経営計画を進めており、2024年度が、3ヵ年の最終年度となる。道産品の拡売やデリカ事業、ドライ事業の拡売などを経営方針に組み込んで取り組んできた同社だが、売上高や利益などの数値目標はクリア、「悪い点数ではないと思う」(黒沢忠寿社長)と言う。しかし、道産品拡売や幹線物流では課題を残した。黒沢社長に、中期経営計画の振り返りと、2025年2月26日に予定されている「春季展示商談会」の見どころなどを聞いた。 〈くろさわ・ただとし〉…1960年1月、江別市出身。酪農学園大学農業経済学科卒、1982年4月、日本アクセスの前身の1社、仁木島商事入社。2012年4月執行役員関東支社長代行兼東京中央支店長、2012年10月執行役員九州支社長、2015年4月執行役員広域営業部門長代行広域チェーン統括、2017年4月常務執行役員東日本営業部門長代行関東エリア統括、2020年1月常務執行役員東日本営業部門長代行関東エリア統括兼長野支店長、2020年3月常務執行役員東日本営業部門長代行関東エリア統括、2020年4月常務執行役員東日本営業部門長代行関東第1エリア統括、2021年4月日本アクセス北海道社長就任。2025年3月末に退任予定。
〈くろさわ・ただとし〉…1960年1月、江別市出身。酪農学園大学農業経済学科卒、1982年4月、日本アクセスの前身の1社、仁木島商事入社。2012年4月執行役員関東支社長代行兼東京中央支店長、2012年10月執行役員九州支社長、2015年4月執行役員広域営業部門長代行広域チェーン統括、2017年4月常務執行役員東日本営業部門長代行関東エリア統括、2020年1月常務執行役員東日本営業部門長代行関東エリア統括兼長野支店長、2020年3月常務執行役員東日本営業部門長代行関東エリア統括、2020年4月常務執行役員東日本営業部門長代行関東第1エリア統括、2021年4月日本アクセス北海道社長就任。2025年3月末に退任予定。
ーー2025年3月期決算の見通しは。
黒沢 2025年3月期決算は、101・4%の増収を予想しており、経常利益も若干の増益になりそうです。一部のコンビニエンスストアの帳合変更によって、その分はマイナスになります。西友さんが、イオン北海道さんに承継されるなど、期初には想定していなかったこともありましたが、そうした影響を勘案しても、増収を確保できそうです。
ーー2024年度は、スーパー各社ともに増収減益の流れになっていますが、卸業界の傾向はどうですか。
黒沢 スーパー各社は、かなり収益環境が厳しくなっていると思います。コロナ禍の際は、外出自粛による内食化傾向の高まりによって、スーパーの売り上げは順調で、利益も取れていました。それが変調してきたのは、3年前のロシアによるウクライナ侵攻のあたりからで、飼料などさまざまなものが値上げになり、円安も進みました。食品は、原材料を輸入していることが多く、メーカーがコスト高で圧迫され、値上げラッシュが起きました。2年くらい前は、値上げになって買い控えがあっても、単価が上がっていたので、スーパー各社の売り上げはそれほど影響を受けませんでした。しかし、以降も値上げが続いており、消費者のマインドには、疲弊感が出ていると思います。
私たちも、運送委託の値上げなどに対応していかなければならず、そのあたりが収益を圧迫しています。また、ベースアップも5%以上実施していますから、固定費も増えています。2024年3月期は、特別損失がありましたが、今年はそれがないために、増収増益にはなりますが、実際の内容としては、それほど良いとは言えない状況です。
ーー2022年度からの第8次中期計画の進捗状況は、どうですか。
黒沢 今年度が最終年度ですが、3年間の中期計画で、売り上げも利益も達成する予定です。計画は、クリアできると考えています。
ーー中期計画のポイントは?
黒沢 中期計画のテーマは、「地域経済の発展に貢献できる北海道NO.1食品卸企業」です。成長事業として、道産品事業を100億円にすることやデリカ、ドライ、業務用に力を入れていくことなどを掲げています。当社は、チルド、フローズンの温度帯商品が強いので、その分野は、さらに強みを増すように力を入れていくことも掲げています。新規ビジネスとして、伊藤忠商事と連携しながら、太陽光発電の導入支援など、ビジネスというよりは、紹介事業を行っています。