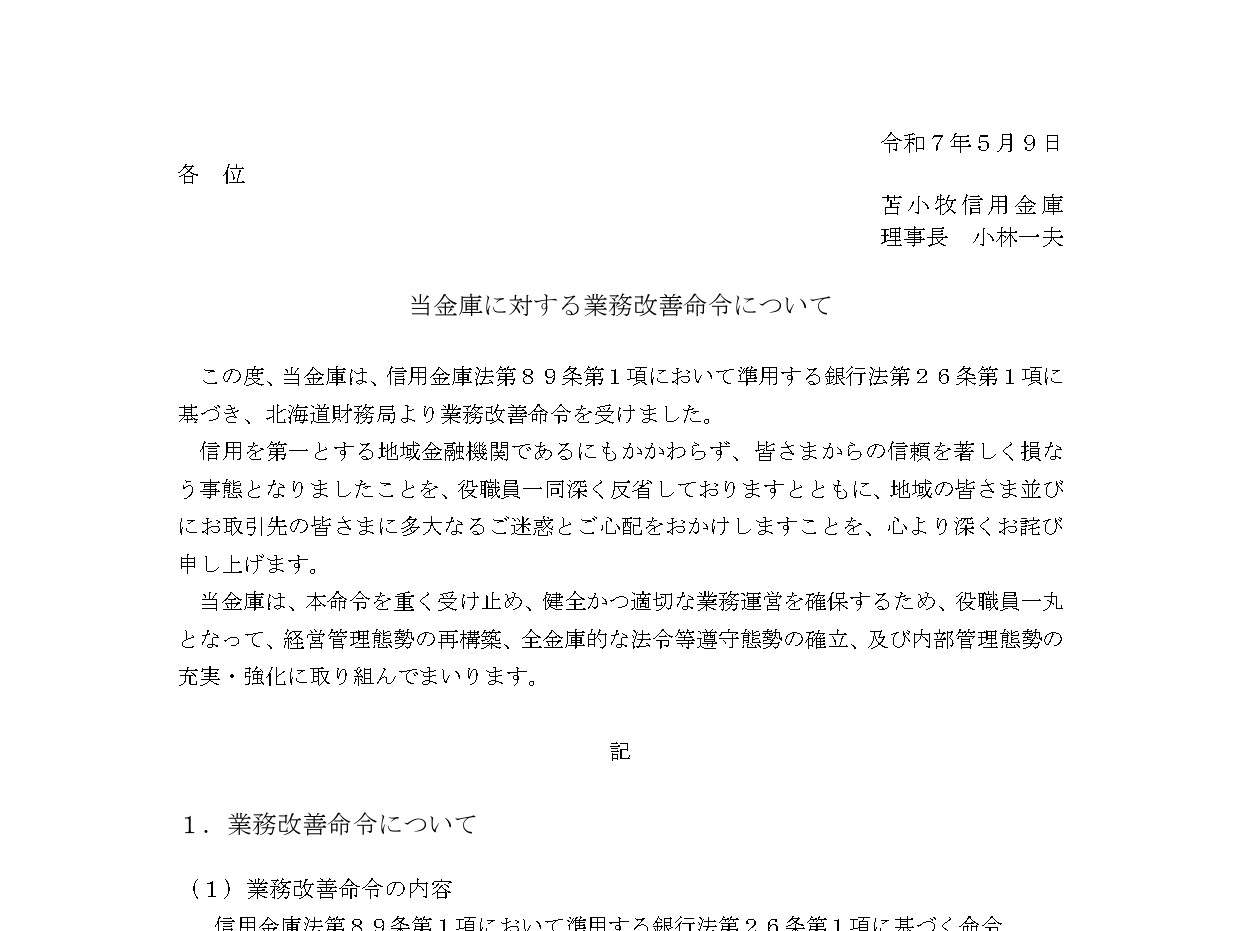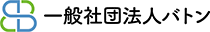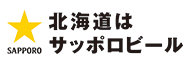──稚内市は、かつて6万人近くあった人口が、今は3万人を切っています。隆盛を誇った水産業も先ほどの200海里問題以降、かなり落ち込んでいます。現在の経済状況をどう見ていますか。
増田 私が入庫した頃は、稚内の人口が5万6千から8千人、宗谷管内で12万人ぐらいでしたが、今は半減しています。となると当金庫も半分に縮小してもおかしくありませんが、1970年代に旭川、1990年代に札幌に営業区域を広げたので、全体の規模は維持されています。実を言うと、200海里前までは、稚内は景気が良く「別に信金などなくてもいい」というまちだったのです(笑)。
ところが200海里問題で取引先の経営が厳しくなると、銀行は融資を引き上げたり、新規融資に応じなくなってきたりしました。そこでリスクテイクをして支えたのが、当金庫でした。その後は、「何かがあっても信金があれば」と、地域で認知をしてもらえるようになった。今もその役割がありますし、これからも地元企業を守り続けていかなければなりません。
規模の縮小というのは恐ろしいもので、まさに足元が崩れていくような感じです。お金だけ出しても地域は守れない。自治体や経済団体などが実施する政策や制度に当金庫も当事者として関わっていかなければ、地域は維持できません。井須さんが理事長だった頃、当時の浜森辰雄市長(1916~2009)とタッグを組んで、さまざまなことに取り組んだのは、今でもとても良いモデルになっています。
私も工藤廣市長と中田伸也商工会議所会頭の3人でタッグを組んで、常に情報交換をしてタイムリーな行動を取れるようにしています。それぞれ役割が違うので、私は「三位一体」と称しています。3人で120度ずつ受け持てば、360度の全方位に対応できます。3人が内側ではなく、外側を向いてお互いの責任を果たすのが大事だという意味で、三位一体と表現しています。
ともあれ地域で人が減っていくのを食い止めるのは、本当に大変なことです。病院があれば人が残るかといえばそうとは限らないし、大学があれば残るかといえばそうでもない。やはり仕事がないとダメなのです。つまり地域でどうやって仕事をつくるか。一時、話題になった地方消滅の議論の時に、宗谷管内で生き残れるのは猿払村だけという報告がありました。他の自治体は皆、消えると(苦笑)。
──猿払村は、水産業がかなり強いですからね。
増田 ホタテを中心としたしっかりした水産業があるから、まちが存続し人も残る。あの村には若い人たちが戻ってきているので、平均年齢が下がっています。子どもの数も増えて就学児童が増えている。ところが稚内の中心街は、シャッター街を通り越して一部がゴーストタウン化しています。これが一番の課題ですが、建物を建てればまちの人口が増えるかといったらそうではない。
悩ましいところですが、ありがたいことに宗谷管内では、20年くらい前から風力発電事業が始まり、その分野では非常に存在感が高まってきました。風が強いという地の利を生かせていることが、競争力になっています。
市長にもよく申し上げているのは、他の地域と同じことで競争する商売をしたら間違いなく稚内は負けると。規模も距離も違うからです。そうではなく、他の地域がやりたくてもできないことに集中しましょうと。だから風力発電は陸上に絞って、洋上には手を出さないでおこうと。
──東京や大阪に信金の出先機関を出し、フェイス・トゥ・フェイスで繋がることは考えていますか。
増田 以前は、東京築地に支店があったらいいねという話をしていました。稚内地域の水産関係は築地との取引があるので、旭川に支店を出すよりは、築地に支店を出した方が良いのはハッキリしていましたが、当時は、店舗規制で実現しなかった。今改めて「いいよ」と言われても出さないですね。
というのも、当金庫が札幌に進出した時もそうでしたが、こちらの事業のための出店でした。札幌に進出して新しい顧客を探すということではなく、こちらの顧客と縁続きのマーケットを対象にした進出でした。そういう意味では、東京とこちらの取引は、限られてしまっています。水産関係も大手水産会社、漁業会社、ぎょれん経由の取引なので、何も築地に行かなくても同様のことが稚内でできます。