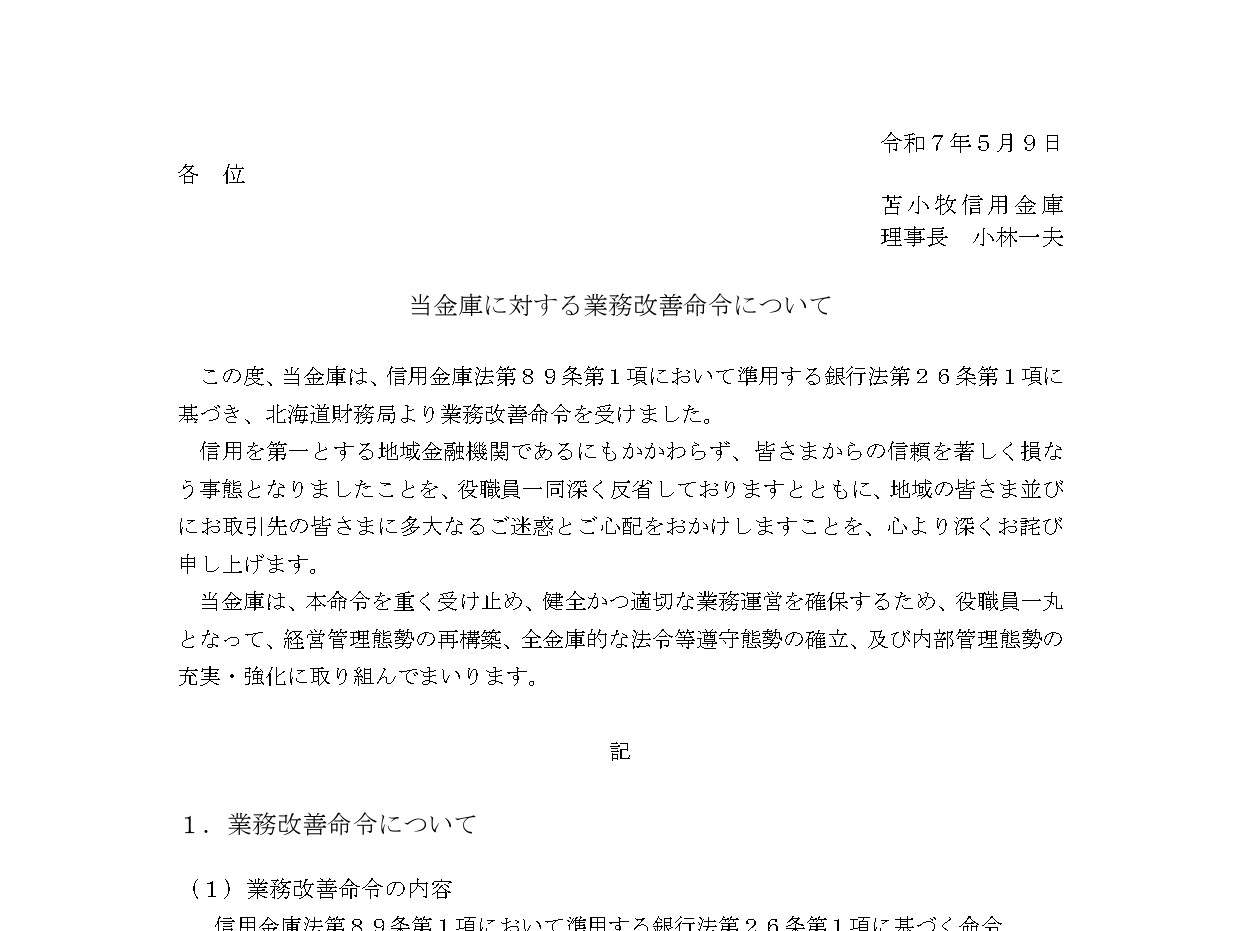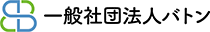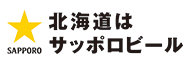日本最北の信用金庫、稚内信用金庫(本店・稚内市)が、2025年10月15日に創立80周年を迎えた。同信金は、戦後間もない1945年、地元商店街有志によって稚内信用組合として設立され、1951年に信用金庫に改組。以後、今日まで宗谷管内の地域経済を支えてきた。その間、地域に激震をもたらした2百海里問題をはじめプラザ合意、バブル崩壊、そして近年のデフレ不況。折々の荒波を乗り越え、常に地元に寄り添ってきたのが稚内信金。創立80周年という大きな節目に当たり、増田雅俊理事長(71)にこれまでの歩みを振り返ってもらい、これからの「ポスト80年」に向けた、あるべき信金像をインタビューした。
 (ますだ・まさとし)1953年11月宗谷郡猿払村生まれ。72年稚内高校卒、78年3月北海道大学法学部卒、同年4月稚内信金入庫。2001年常勤理事業務推進部長、2004年6月常務理事総務部長、2006年6月から現職。71歳
(ますだ・まさとし)1953年11月宗谷郡猿払村生まれ。72年稚内高校卒、78年3月北海道大学法学部卒、同年4月稚内信金入庫。2001年常勤理事業務推進部長、2004年6月常務理事総務部長、2006年6月から現職。71歳
──戦後80年の今年、稚内信金も創立80周年を迎えました。
増田 先の大戦が終わった直後に初代理事長の高橋善之助さんをはじめ、地元商店街の6人で信用組合を設立したのが始まり。それが1945年10月15日だったので、その日が創立記念日になりました。51年に信用金庫法が施行されて、信用金庫に衣替えしたという流れです。高橋善之助さんは、初代と3代目の理事長に就き、4代目が井須孝誠さん、5代目が佐野日出勝さん。そして6代目の理事長が、私になります。
──増田理事長が入庫されてから現在に至るまで、実にさまざまな出来事がありました。
増田 1978年に入庫して最初の大きなインパクトは、200海里排他的経済水域の施行でした。実は、入庫してから分かったのですが、前年の1977年にこの規制が施行されていたのです。まちの経済に大きな衝撃が走っていたのに、私は何も知らずに入庫してしまった(笑)。
その後は1985年のプラザ合意ですね。マーケットの仕事を担当するようになって1年経たない頃にそれが起きました。続く1987年のブラックマンデーの時は、まさにプレーヤーとしてど真ん中にいたので衝撃は大きかった。当時、金庫には株価ボードがありましたが、それが真っ赤になったのを覚えています。
それからバブル経済。ようやく金融政策などが分かるようになってきた頃、1990年の入り口で株価大暴落、いわゆるバブル崩壊です。1989年の年末は、かなりの株など有価証券を保有していた頃で、年が明けて一挙に株価が下がりました。何もできず、じっとしていたのですが、幸いなことにその後リバウンドしたので、その年の4月、一気にほぼ全ての保有株式を処分しました。
当時の井須理事長に「売りましょう」と提案したら、即決でOKを出してくれた。私は毎朝、井須さんと話をしていたので、コミュニケーションの効果がここで出ました。「あなたがそう言うなら、いいんじゃないか」と。損失も出ましたが、ほぼ全ての株を売り切りました。
──その後も持っていたらどうなっていたか分からない。
増田 今にして思えば、当金庫は、存続していなかったかもしれません。それぐらい大量に保有していました。当金庫は預貸率(預金残高に対する貸出金残高の比率)が低く、預証率(預金で調達した資金のうち、どれだけ有価証券で運用しているかを示す比率)が他の金庫より高かったですから、あのまま持ち続けていたら大変なことになっていたでしょう。その時、やり方一つで金庫は潰れてしまうということを、はっきり自覚しました。
私は、若い頃に心室中隔欠損症という心臓の重い病気を経験しています。当時は、文字通り「もしかしたら明日はないかもしれない」という覚悟で生きていました。決めたらすぐにやらなければ気がすみません。井須さんと短時間で重要な決定を下せたのは、以前から上司と部下として意思疎通がきちんとできていたからでしょう。その即断即決が功を奏して、あの時の危機を切り抜けることができました。