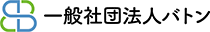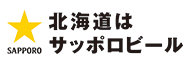大地みらい信用金庫(本店・根室市)の新理事長に、伊藤哲也常務理事が昇格してから半年、伊藤カラーが徐々に出てきた。就任時は48歳と、道内信用金庫の中では、その若さでも注目されたが、常勤理事、常務理事時代は、経営の中枢部門ポストを歴任するなど、順当な人事だったことが、うかがわれる。地に足の着いた地域密着の視線は、若い頃の経験が糧になって生きている。信用金庫が、地域経済に果たす役割とは何か、伊藤理事長にインタビューした。 〈いとう・てつや〉…標津郡中標津町出身、49歳、1998年3月北海学園大学経済学部卒、同年4月根室信用金庫入庫、2013年4月白糠支店長、2016年4月経営企画部長、同年6月常勤理事、2018年6月常務理事、2024年6月理事長。
〈いとう・てつや〉…標津郡中標津町出身、49歳、1998年3月北海学園大学経済学部卒、同年4月根室信用金庫入庫、2013年4月白糠支店長、2016年4月経営企画部長、同年6月常勤理事、2018年6月常務理事、2024年6月理事長。
ーー入庫の経緯をお聞かせください。
伊藤 1998年3月に、北海学園大学経済学部を卒業しましたが、当時は就職氷河期で、同期の学生たちも20社、30社を受けるのは当たり前でした。私は、金融機関や出版関係に興味がありました。というのも、NHK札幌放送局報道部で3年間アルバイトをしていたので、そちらの道にも進みたいと思っていました。迷っていましたが、いくつかの金融機関を受けて、当時の根室信用金庫(現大地みらい信用金庫)の内定をいただきました。ゼミの教授と相談して、入庫することに決めました。
ーー入庫以降の経歴は。
伊藤 中標津支店を皮切りに、釧路市内店、根室での本部勤務の後、白糠町で勤務をさせていただきました。営業担当として「海」の街も「山」の街も勤務をさせていただいたことで、基幹産業である水産加工・酪農業のみならず、林業・建設業・製造業・小売卸業などの多くの産業のお客さまと接することができました。
本部では、審査部と営業推進部といった「攻め」と「守り」の部署を経験させていただきましたが、営業推進部への異動が、東日本大震災発生の翌年で、その際に企画した定期預金「みらいの架け橋」が、強く印象に残っています。両親を震災で亡くした子どもたちの夢を実現するために、高校卒業後の進学を支援する奨学基金として設立された「みちのく未来基金」に、利息の一部を寄付するという金融商品でした。募集を始めたところ、多くの反応をいただきました。
ーー「白糠支店」支店長を経て常勤理事、常務理事、そして48歳で理事長になられた。道内信金の中で、40歳台での理事長就任は珍しい。
伊藤 支店長として勤務した白糠支店では、金庫の代表として、街の関係者と接する店長のダイナミズムを学ばせていただきました。役員に就任して以降は、本部各部で部長や担当役員を経験させていただいたことで、金庫の業務全体を俯瞰して見られるようになりました。理事長就任については、昨年までは専務理事がいましたし、新体制では、私の役員経験が8年と一番長いので、抜擢というよりも、巡り合わせ、縁みたいなものではないかと、私自身は思っています。
ーー理事長に選ばれた時は、どう受け止めましたか。
伊藤 びっくりしました。私自身、能力がそんなに高くないのを自覚しています。私よりも、それぞれの分野で能力の高い役員がたくさんいますので。