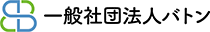札幌スイーツの代表格として知られる「きのとや」。今から30年前、喫茶店としてスタートした同社は切羽詰まって始めたケーキの宅配が当たり成長のきっかけを掴んだ。いくつもの偶然を事業の芽になると感じ取る嗅覚とそれを育てていく野太さ――「きのとや」誕生の裏面史を長沼昭夫社長(65)が余さずに語った。今回はその1回目。(6月4日に行われたキャリアバンクと読売新聞北海道支社の共同企画「朝活」の講演を構成。写真は、講演する長沼昭夫氏)
札幌スイーツの代表格として知られる「きのとや」。今から30年前、喫茶店としてスタートした同社は切羽詰まって始めたケーキの宅配が当たり成長のきっかけを掴んだ。いくつもの偶然を事業の芽になると感じ取る嗅覚とそれを育てていく野太さ――「きのとや」誕生の裏面史を長沼昭夫社長(65)が余さずに語った。今回はその1回目。(6月4日に行われたキャリアバンクと読売新聞北海道支社の共同企画「朝活」の講演を構成。写真は、講演する長沼昭夫氏)
長沼社長は、北大水産学部を卒業し学生時代の先輩を頼り新冠町新栄で農業を始めたのが社会人としてのスタート。離農地を買い、乳牛や肉牛の肥育、養鶏、養豚、畑作を手掛けたが軌道に乗らず4年間でドロップアウト、札幌に戻った。
居酒屋の店長や学生時代に鍛えた山スキーの経験を活かしてスキー場の従業員になったが、ある日新聞広告でダイエーの募集を見つけた。「人生をゼロからやり直そうと考え応募したら採用が決まった。当時29歳、本当にゼロからのスタートだった」と長沼氏は言う。当時のダイエーは破竹の勢いで拡大しており、創業社長の中内功氏も年に1~2回は北海道の店舗を視察に来ていた。「カリスマ経営者の中内社長に憧れていましたね。下っ端の社員でしたが会うのが楽しみで、感動しながら店舗の隅から眺めていました」
しかし、長沼社長はダイエーを5年間務めて退社する。「ダイエーは関西に本社があって幹部も関西弁を喋るし、道産子の私はどうにも馴染めなかった。それにサラリーマンの限界も感じていました」
そのころ、義父が東札幌で2階建ての自宅を新築、1階のスペースにケーキ屋をテナントとして入れたいと相談をもちかけられた。当時、長沼社長は自分がやることなど考えてもいなかったという。相談を受けてから1年経っても入るテナントが決まらない。ダイエーを辞めたタイミングとも重なり、「ケーキを作ることもできないし伝手もないから私が喫茶店をやってケーキを仕入れて売ることにしました。義父は小樽の駅前にあった国際ホテルの『ロートレック』という喫茶店の雰囲気が良いというので一緒に見に行き、ついでに小樽のケーキやお菓子の繁盛店として知られていた『館』や『あまとう』を訪れたことを思い出します」
喫茶店を開いて、ケーキを仕入れようとしたらどこも売ってくれない。結局、近所の顔見知りのケーキ屋に頼み込んで何とか置くことができた。
16席の喫茶店で長沼社長はコーヒーを淹れ、パートの女性にケーキ販売を任せたが、お客が入らない。「10時間営業していましたが1日10人来れば良い方だった。ケーキを仕入れてももちろん売れないから捨てる方が多かった。パートの女性から『何をしたらいいでしょう』と言われたり、お客を待つことの辛さが骨身に染みました」
学校が近いこともあってパンなら売れるかもしれないと置いたが、これも全く売れなかったという。
ケーキを売る方法はないかと考え続ける毎日。閃いたのはバースディケーキの予約を取って自ら作ることだった。「計画的にやったのではなく、お客が来ない辛さに耐えられなくなってこちらから出向いて予約を取ることにしました」
ところが、東札幌の聞いたこともない店のケーキなど誰も注文してくれない。車を持っている女性を雇って歩合制で1年先でも予約を取るようにした。見本で作ったケーキを持って行き試食してもらい何とか注文が入るようになったが、わざわざ店まで取りに行けないという声が多く、当時はどこもやっていなかった宅配をすることに。
「バースディケーキのパンフレットを作って営業3人を雇い、1年間で1000個の予約が取れました。1日3~4個の注文です。私にすればすごいことでした。こうすれば予約が取れるということが分かりましたね」
宅配のエリアを定めず、片道1時間かかっても届けるようにして、紺のスーツに蝶ネクタイで運ぶ趣向も取れ入れた。近くにケーキ屋のない遠いところでも届けるサービスやお誕生日に集まった近所の子供たちが自分の誕生日にも同じものを食べたいという声が多くなって、「まるで核分裂のように予約が増え始めたのです。それと並行して店にもケーキを求めるお客が増えていきました」
(以下、次回)