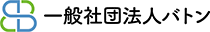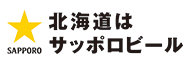2023年4月に函館市長に就任した大泉潤氏(59)が、1期目の任期折り返しを迎えた。就任早々に人口減少対策本部を設置するなど、中核市でもある函館の人口減少には強い危機感を抱き、国だけに頼らない市独自の施策を充実させてきた。北海道新幹線札幌延伸が遠のき、公約である函館駅乗り入れも見通せなくなったが、今まで以上に力を入れると一歩も引かない姿勢を見せる。行政出身ながら市民目線に立脚する市政への向き合い方は、大泉カラーと言えるものだろう。大泉氏に函館市の今をインタビューした。 〈おおいずみ・じゅん〉…1966年3月、江別市生まれ、59歳。札幌北高、早稲田大学法学部卒、函館市役所入庁。2017年4月観光部部長、2019年5月保健福祉部部長、2022年7月市退職、2023年4月市長就任、好きなアーティストはGLAY。
〈おおいずみ・じゅん〉…1966年3月、江別市生まれ、59歳。札幌北高、早稲田大学法学部卒、函館市役所入庁。2017年4月観光部部長、2019年5月保健福祉部部長、2022年7月市退職、2023年4月市長就任、好きなアーティストはGLAY。
ーー市長就任後に設置された人口減少対策本部の取り組み状況について。
大泉 人口減少対策について、私が市長に就任する前まで統括する部署がありませんでした。予算編成時に人口減少を止めなければならないという力が各部署にかからないまま、次年度事業の構造ができ上がっていき、予算発表時には、それらしい施策をピックアップして、人口減少対策と称するのが通例でした。人口減少は、全国で起きており、国が動かなければどうしようもないという考えがあったからです。
しかし、私の考え方は違っています。函館は、全国で起きている人口減少のレベルではありません。中核市の中で最速、最悪のスピードで減っており、危機的状況です。国に任せるのではなく、自分たちの視点で、ボトムアップで人口減少を抑止する事業を考えることが絶対的に必要です。それが、人口減少対策本部を立ち上げた目的で、移住・定住の促進、子ども・教育への支援、仕事の創出を3本柱として、それぞれ専門部会を設けています。すでにさまざまなアイデアが出て、予算をつけて実行しています。
ーー成果は出ていますか。
大泉 人口減少対策について、地域全体の手応えが大きく、潮目が変わったと感じています。私が市長に就任して2年半が経ちましたが、函館が、国内外から注目される時期と重なりました。特に、2024年は、そういう年だった。観光をはじめとする賑わいもそうですが、さまざまなメディアで取り上げられるなど、函館に関する関心が非常に高まりました。市職員も地域の人たちもそのことを感じ、自分たちの潜在力を信じることができるようになったのではないでしょうか。それが、潮目が変わったと私が感じているところです。
ーーコロナ禍を超えて観光客が回復、“コナン効果”もあって注目が集まりました。市長自身が、潮目が変わったと感じるほどの変化なのですね。
大泉 函館に進出してくる企業も、2023年度、2024年度は、これまでの倍近くになっています。
ーー人口減少対策に繋がる子育て、教育に対する支援について。
大泉 就任2年半ですが、子育て制度は大きく変わりました。市独自の施策もあれば、国、都道府県で改善した制度を踏まえると、劇的に変わっています。妊娠する前の不妊治療に対する支援から始まり、教育費のピークである大学の学費として、地元学生限定ですが、公立はこだて未来大学の無償化を行っています。就学前、小学校、中学校と、さまざまな段階で子育てに関する支援制度は充実しています。
例えば、不妊治療の負担分のうち、市と道で7割を支援していることから始まって、妊娠したら妊婦1人に5万円の応援給付があります。生まれたお子さん1人に5万円の応援給付があって、保育料も第二子以降は完全に無償です。小学校に入学したら、子ども1人に10万円のサポートも市独自で行っています。学童保育の支援も引き上げています。
大事なのは、こうした施策を市民に伝えていくことです。皆さん忙しいので、支援があるということに気づかないかもしれないからです。スマートフォンで申し込めるように分かりやすくつくり込んで、特に子育て世帯が必要としている制度は、スマホで完結できるように力を入れています。
ここで子どもをつくろうとか、家族をつくろうと思う若い人には、大変な覚悟が要ります。その際に、「この街は守ってくれる」という姿勢が伝わらないと意味がありません。制度を整えて、市の考え方や充実した制度を発信して伝えることがすごく大事なので、支援パッケージの名称を「ウェルビーイング22」として、今年度中にそれをつくって伝えていきます。