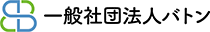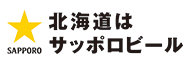心が通じ合うとき、人は笑顔になる。ささくれ立った心が穏やかになる。人は人から元気をもらうとき、元気をあげるときが一番輝いている――そんな思いを強くした。
20日、札幌テイネ聖火台オーシャンコースで開催された「第32回全道ハンディキャップスキー大会」兼「札幌大通ライオンズクラブ杯ハンディキャップスキーメモリアル大会」。障害者と健常者がともに作り、競い、喜び合うスキー大会は、かけがえのない心の交流を運んでいた。(写真は左・スキー競技をする身障者、右・表彰式)
身体にハンディを負った人や目の不自由な人、知的障害の人など、この大会には毎年60人以上が参加する。
スキーを楽しむというレベルを超え、記録に挑む人たちの眼差しはスポーツマンそのもの。そこには、身体からはみ出るような心の強さがあふれ出ている。
全道ハンディキャップスキー大会は、1980年、三笠宮寛仁親王の呼びかけによって始まった。障害者の社会参加の機会を作るために活動していた寛仁親王が、北海道の冬を楽しむスキーを通じて障害者に喜びと自信をもってもらいたいという思いから始まった。
札幌大通ライオンズクラブが運営に携わるようになったのは15年前。当時の鉄川昭会長が数多くの身障者スキー大会に参加していた会員の野呂幸司氏に相談し、共催にこぎ付けた。
大会の規模やボランティアの確保、そして予算面からライオンズクラブが携わるのは1回限りと見られていたが、実際に大会を開くと障害者たちの生き生きとした姿にライオンズクラブの会員やボランティアたちは深く胸を打たれる。
なにより、参加した障害者同士が「また来年もこの大会で会おう」と声を掛け合い、楽しみにしていることが分かるとライオンズクラブ会員たちの心は動いた。
「困難があっても継続して行うことが、障害者の励みになる」――自ら障害者として身障者冬季五輪にも出場した経験のある野呂氏をはじめ会員の有志たちは、この大会をクラブ結成の事業として取り組むことを決めた。
2回目からは、札幌稲雲高校の教師と生徒たちがボランティアとして大会運営に参加、今年も82人の生徒たちが大会を通じて障害者と一緒に大会を盛り上げた。
スキーの技量に応じて上級、中級、初級に分かれ、実際にアルペンのタイムを競う種目と申告したタイムと実際のタイム差の近さを競う種目で行われ、選手たちは1本スキーやチェアスキーなど日ごろの練習の成果を出し合った。
昨年は強風でリフトが動かずに中止になったが、今年は気温も例年以上、春を感じさせる陽光が注いだ。参加者たちは2年分の思いを乗せて風を切っていた。
表彰式では各部門の上位3位までに記念の盾やメダルが授与されたが、どの顔にも一点の曇りもない晴れやかさがあった。
この大会に継続して参加して実力をあげ、今年2月にフランスのランスで行われた国際知的障害者スポーツ連盟主催の「第3回アルペンスキー世界選手権」で大回転、スーパー大回転2種目で銅メダルを獲得した田川聡史氏も顔を見せ、参加者たちの熱い視線を浴びていた。
 (写真は、右・田川氏 左・野呂氏)
(写真は、右・田川氏 左・野呂氏)
多くの関係者やボランティアたちの支え合う気持ちが大会の継続を底辺で支えている。寄り掛かるのではなく、一人ひとりが自立して協力し合い、参加する障害者とともにより大きなものを作り上げていくコミュニティの力がそこにはある。
スキー大会でありながらそれ以上の心の鼓動を身体で感じることができた。自然と込み上げてくる想いは、何の発露なのか、自問しながら山を降りた。