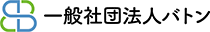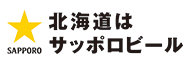一般社団法人日本加工食品卸協会(東京都中央区、略称・日食協)北海道支部の2025年度交流会が2025年10月30日、札幌市中央区の札幌グランドホテル2階グランドホールで開催された。食品卸やメーカーなど約100人が参加した。 (写真は、日食協北海道支部交流会で挨拶する齋藤伸一支部長)
(写真は、日食協北海道支部交流会で挨拶する齋藤伸一支部長)
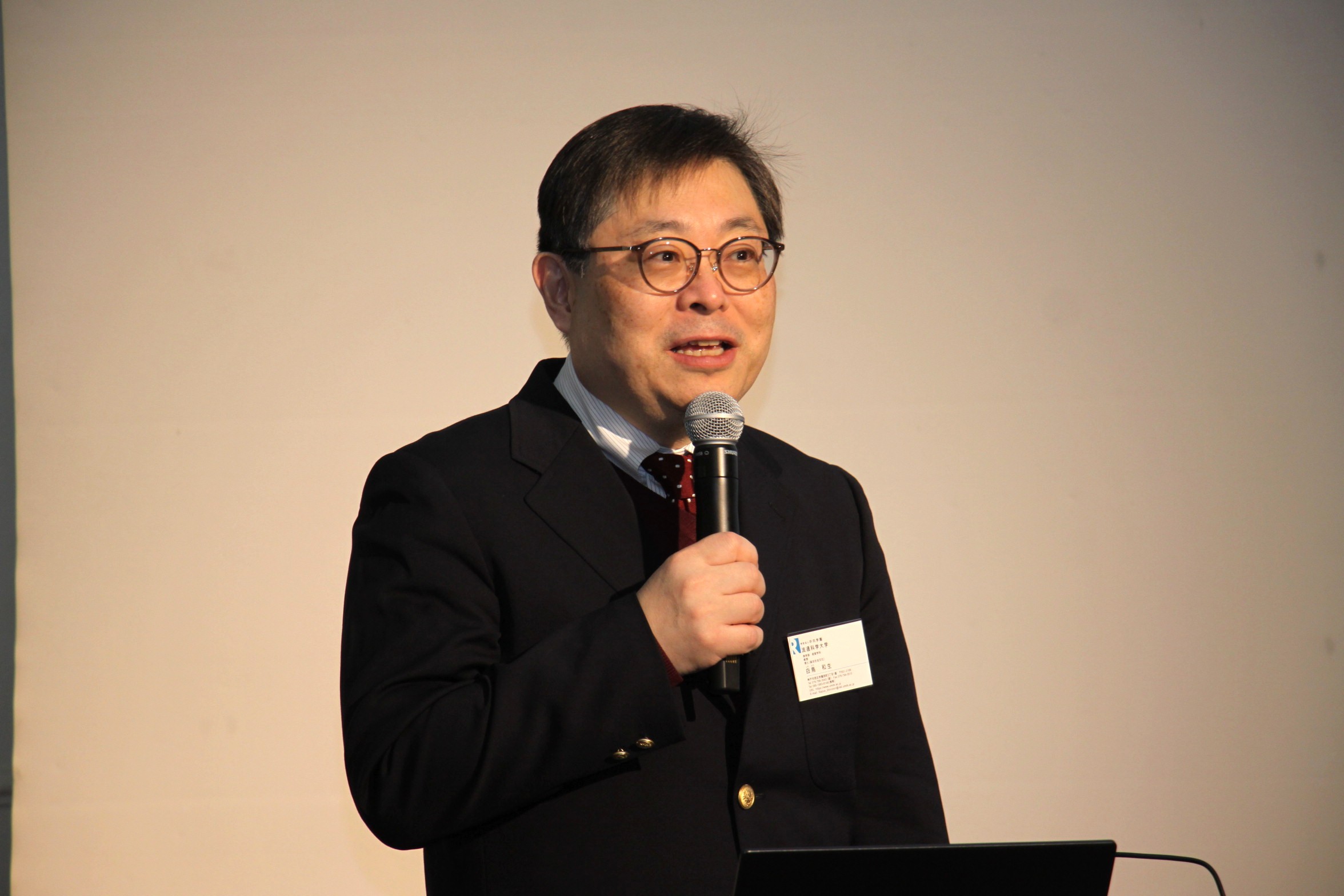 (写真は、講演する流通科学大学の白鳥和生教授)
(写真は、講演する流通科学大学の白鳥和生教授)
冒頭、日食協北海道支部長の齋藤伸一・日本アクセス北海道(本社・札幌市東区)社長が挨拶。斎藤氏は、「加工食品業界の積年の課題であった製配販の非効率な情報連携にテコ入れすべく、当協会が事務局となり、次世代EDI協議会を発足させ、業務効率化と生産性向上を目指す取り組みを進めている。皆さまの協力を得ながら、課題解決に向けて前進したい」と話した。
続いて、日食協の時岡肯平専務理事が「加工食品サプライチェーンの現状と課題」をテーマに活動報告を行った。時岡氏は、24社が参加して、7兆円規模のスーパーが横連携しているSM物流研究会について、①パレット納品の拡大②共同配送、空きトラックの有効活用③生鮮物流における物流課題の解決④チルド物流における物流課題の解決について検討、着実に進展している状況を説明した。
また、メーカー・卸間で、見積情報・商品マスタ情報の授受をデジタル化し、フォーマットの共通化や自動変換・出力を行うことで、提出先小売業ごとの個別対応、担当者ごとの重複作業を削減してサプライチェーン全体の全体最適を目指す「N-Sikle」(日食協商品情報連携標準化システム)の将来構想も示した。
講演は、白鳥和生・流通科学大学商学部経営学科教授が、「人口減少下における流通業界の課題-進む小売再編にいかに対応すべきか」と題して行った。白鳥氏は、人口減少、少子高齢化、デジタル化の進展により、小売業は、スケーラブルな再編を進めていることに触れ、「商品調達力やPB開発力、物流・デジタル対応、市場の変化などが再編の軸だが、勝ち馬に乗りたいスーパー経営者などの最後の駆け込みも、再編の軸になってきた」とし、ヤオコー(本社・埼玉県川越市)の持ち株会社、ブルーゾーンホールディングス(同・同)を紹介。
「ブルーゾーンは、東京の文化堂と愛知県のクックマートを傘下に入れた。ヤオコーは、インクが染み込むような隣同士の再編ではなく、飛び地での再編戦略を明確にした。地方のスーパーにとって、店格の高いヤオコー入りも選択肢になるのは間違いない」と話した。また、商圏が狭小化していることに対して、「高齢化社会では、半径300mの商圏が現実になってくるため、小売業は、リアル店舗を生かした、よろず相談窓口になることが求められる。来店客の困りごとを他社に繋ぐネットワークのハブになれば、手数料収入というフィービジネスも加えることができる」と述べた。
さらに、サブスクリプション型ビジネスモデルについて、「コストコは、会費収入で営業利益の半分を稼いでいる。成城石井も入会費1万1000円の有料会員制プログラムを6店舗に拡大した。サブスク的な発想が収益を上げる」とした。