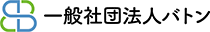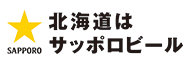日本最北端のまち、稚内市でのローソンVS.セイコーマートが、全国的な話題になっている。攻めるローソン、守るセイコーマートの対決構図に関心は高まるが、地元や北海道では、冷静な受け止めが多い。というのも、日常生活にすっかり定着したコンビニエンスストアの競争環境が変化しているためだ。北海道や本州の埼玉県・茨城県で進化を続ける地域特化コンビニ“セイコーマート”の今とこれからを、セコマ(本社・札幌市中央区)の赤尾洋昭社長にインタビューした。
 《あかお・ひろあき》…1976年10月札幌生まれ、48歳。北嶺中・高校、一橋大学卒。1999年4月マツダ入社、2004年5月 セイコーマート(現セコマ)入社。2006年3月取締役、2009年2月常務、2014年2月専務、2016年2月代表取締役副社長、2020年4月社長就任。
《あかお・ひろあき》…1976年10月札幌生まれ、48歳。北嶺中・高校、一橋大学卒。1999年4月マツダ入社、2004年5月 セイコーマート(現セコマ)入社。2006年3月取締役、2009年2月常務、2014年2月専務、2016年2月代表取締役副社長、2020年4月社長就任。
ーー2025年12月期の業績予想は。
赤尾 2024年12月期は、2023年の特別利益を除くと増収増益となりました。売り上げは、2021年の1680億円から1970億円になりました。今期は、5%程度のインフレによる売上増加を予想しています。各方面で人への投資を重点的に行っており、戦略的に減益とする予定です。
ーー消費傾向に変化はありますか。
赤尾 前期は卵不足があり、今期はコメ不足ですが、いずれも需給逼迫によるもので、消費トレンドの変化とは言えませんね。雑誌の取り次ぎが日販からトーハンに変わり、毎年前年比85%で減少を続けてきた雑誌は、減少が止まりました。また、RB(リテールブランド、プライベートブランドと同義)商品が伸びており、売り上げを牽引しています。
ーー競合コンビニとの関係に変化はありますか。
赤尾 あまり他のチェーンの影響を受けなくなってきました。駐車場を拡大したり、大通のほくほく札幌ビルの地下のようにセイコーマートの空白地帯に出店すると、集客が増えますが、それは競合からお客さまが来るというより、本来セイコーマートに行きたいけど、入れなかったお客さまが来店できるようにようになったためです。タバコは免許制なので、一定程度は競合しますが、その他の商品は、他社が出ても当社は減らないし、当社が出ても他社も減らないのではないでしょうか。
ーー稚内市では、ローソンが強気の出店をしています。稚内市の状況をどう見ていますか。
赤尾 昨年8月にローソンが進出して4店舗になり、さらに今年6月に3店舗を新規出店しています。6月は、セイコーマートの既存2店舗の間にローソンが出店しましたが、2店舗ともにあまり影響を受けませんでした。関係あるのかどうか分かりませんが、当社と長年すみ分けを図ってきた地元企業の業績が最近悪化しているようです。
ーー稚内市のセイコーマートは18店舗、ローソンは7店舗で、コンビニは市内で25店舗になりました。今後のセイコーマートの再編集約はありますか。
赤尾 現時点で具体的に考えていることはありません。移転が決まっている店舗もありますが、閉店予定はありません。私は、ドラッグストアの影響が大きいと見ています。稚内市にツルハさんの大きな店舗ができた時は影響を受けました。
他の地域でも、似た状況になってきました。コンビニ産業は成熟してきて、店舗数が増えていく状況ではありません。店舗のフォーマットが固まってきて、大きな商品構成の入れ替えがなく、お客さまの使い方も決まってくる中で、各社ともに固定客化が進んでいます。そういう意味では、新規に出店することによって売り上げが減るのは、どこも自社の近隣店舗であって、他社から移る人は少ないと思います。
ほとんどのお客さまは、2つくらいのコンビニチェーンを使い分けています。メインとサブのチェーンという使い分けで、セイコーマートをメインにしている人は、3割くらいいると推察しています。全国チェーンをメインで使う人は5割くらいいて、残り2割の人は、コンビニ、スーパー、ドラッグなどを気にせず使う方です。もっと増えてほしいが、一つの会社で独占することはできません。お客さまの嗜好もいろいろありますから、ゆっくりと増えていけばよいと考えています。セイコーマートに行きたいが、近くに店舗がないお客さまがまだ相当数いますので、そのお客さまを深掘りすることよって売り上げはまだ拡大する余地があると思います。