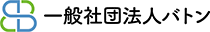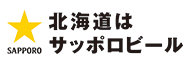ーー店舗事業は、黒字化が課題です。
大見 店舗事業の黒字化に向けて、決して旗を降ろしているわけではない。コロナ禍で一時、黒字化したが、(黒字化の定着は)そう簡単にはいかない。コープさっぽろの店舗にはリース物件が多い。毎年2~3店舗の建て替えをしていますが、そのタイミングで店舗を自前化しています。土地も自前にすると、さらにコスト構造が変わります。だけど、フルリースでは20億円の売り上げでも赤字になっている店舗があります。加えて昨今は、食品値上げと人件費上昇によって、収益性を維持することは簡単にはいかない。店舗事業の黒字化は持久戦です。
業界的に見ると、こういう時期には、再編統合が起きます。とりわけ、地方の店舗は厳しい状況が続いており、グループの中央スーパー(留萌市)は投資しなければならない店舗については、遠別町、増毛町の店舗のようにコープさっぽろの店舗にしています。地域に1店舗しかなくて、チラシを打たなければ、こうした地域の店舗も黒字になります。2025年9月に閉店する東神楽町の農協系店舗も、承継して「コープさっぽろ」の店舗にする考えです。
ーー新店舗の「コープさっぽろとっとり店」について。
大見 大型ホームセンターの「ジョイフルエーケー釧路店」と、ヤマダデンキの大型店「テックランドジョイフルタウン釧路店」が集積しており、広域から来店客が見込めます。こうした大型店の集積は、今後それほど出てこないため、出店を決めました。店舗は自前で建設しており、「無印良品ジョイフルタウン釧路店」もコープさっぽろが建物を建設しました。コープさっぽろの店舗は、売り場面積約650坪でドラッグコーナーも設けており、2025年6月に建て替えオープンした「コープさっぽろのっぽろ店」(江別市)と同じ規模です。
コープさっぽろは、釧路市内で2011年5月に「新橋大通店」を出店して以来、新規出店をしていません。10年以上にわたって、新規出店または建て替えをしないと、その地域での競争力が低下してしまいます。釧路のように、地域の出店政策を再構築する取り組みを昨年から進めています。来年は、函館で、店舗網を再構築します。
ーーグループ企業の売り上げ規模はどれくらいですか。
大見 2024年度で800億円弱になりました。コープさっぽろ本体と合わせると4000億円弱になります。グループの物流系で250億円規模になっており、電力・エネルギー系も200億円を超えてきました。生産工場系も全部入れると200億円を超えています。生産工場系については、道内の食品メーカーで、経営者の承継を含めて経営的に苦境に陥っているところがあれば、救済支援で統合する方針で臨んでいます。
私たちは、小売業として人口減少社会の中で、どんな所に住んでいても食材を提供できる体制を既に実現しています。その次に来るのは、地方の雇用問題。道内の一次産品に付加価値を付ける地方の食品メーカーが存続できれば、引き続き地方の雇用を確保できます。その代表例が、クレードル興農(札幌市中央区)やさくら食品(小樽市)、森谷食品(釧路市)です。これからも話があれば、対応していきます。
ーー1998年の事実上の経営破綻を経て、コープさっぽろは大きく変化、発展してきました。
大見 グループとしてポートフォリオを描けるようになってきました。これは大きいと思います。小売単体からグループの事業をどう成長させるかなど、利益構造が描けるようになってきたのは、大きな進歩だと思います。
ーーさらに描いている青写真は。
大見 準公的機関の学校系や医療系の分野で決済機能、物流機能、生産機能をどう生かしていくかを考えたい。医療分野にも力を入れます。未病管理(病気ではないが、健康状態でもない「未病」の状態を、健康な状態に改善するための管理活動全般)などを行って、北海道の医療費減額に結び付けるとともに、道民の健康寿命延伸にも貢献したい。健康診断事業に参入したのは、そういう目的からです。医師も現在は、4人在籍しています。その他には、道外からの移住を進めるため、市町村と連携して取り組むことも考えています。
ーーコープさっぽろグループ全体の売り上げ目標は。
大見 数値目標は、決めたらだめではないかと思っています。世界情勢や気候変動から見ても、これから何が起こるか分かりません。誰も将来を想定できないと思いますよ。(終わり)