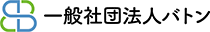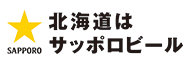道を筆頭株主とする新生HACが4月にスタートばかりだが、奥尻空港での地上30mへの異常接近は重大インシデントとして同社の信頼を大きく損ね、経営面では早くも増資もしくは新たな借り入れが避けられない情勢になってきた。
道を筆頭株主とする新生HACが4月にスタートばかりだが、奥尻空港での地上30mへの異常接近は重大インシデントとして同社の信頼を大きく損ね、経営面では早くも増資もしくは新たな借り入れが避けられない情勢になってきた。
新生HACと言っても、株主と資本金など外形的変化と路線、拠点空港の丘珠集約など運航上の変化があっただけで、肝心の内部、つまりコンプライアンスやガバナンスの面では旧態依然とした状態が続いている。今回の事故は外とともに内部の大掃除も必要だということがハッキリした。(写真はHAC機)
HACのカバナンスやコンプライアンスを疑問視するような声は、実は以前から指摘されていた。
そのひとつがJALからHAC役員として出向してきた機長のパワハラまがいの言動。この機長は、現在も役員として新生HACの経営にあたっているという。
かつて副操縦士として同社に勤務していたA氏は、「高圧的で差別を繰り返し、会社や操縦室ではモノが言えない雰囲気だった。JAL時代には全副操縦士から乗務拒否を受けたような機長なのに、HACが受け入れて役員に登用したことに絶望を感じた」
また、1日のランディング回数に関する指摘もある。1日10回まで国に申請して認められているが、8ランディング、少なくても6ランディングで身体を壊す乗務員もいたという。5~6年前にプロペラ機を使用していたエアーニッポンネットワークや日本エアコミューターなどと比較しても、飛行時間やランディング回数はHACが一番多かったときもある。
前出の副操縦士は、「他社に比べても様々な面で劣悪な環境であったけれども、手当てがなくて待遇改善は望めなかった。業界でも最低ランクの待遇に特にプロパー乗員の不満は溜まっていた」と語っている。
また、JALが大株主だったころには、親会社を退職して天下りしてきた機長や出向の乗務員とプロパー乗務員とでは給与面でも格差があり、その格差は埋まらなかったという。
新生HACになって、JALが大株主から撤退して一株主の立場になり、JALグループとして受けていた様々な優遇措置がなくなった。発券システムの構築や機材整備など自前で取り組まなければならず、新生HACのコスト負担は従来よりも多くなるのは避けられない。
そんな中での重大インシデントでトラブル機の運休に伴う収入減少、エンジン交換費など臨時費用によって、「経営への影響は小さくない」(道の武田準一郎建設部長)。事故対応如何によっては、道民の翼としての信頼が取り戻せない可能性も残る。
新生HACは原因究明と再発防止に取り組むのはもちろんだが、最も大事なのはカバナンスやコンプライアンスの大掃除だろう。新生HACづくりを急がなければならなかった不運が引き起こした波乱をどう乗り越えていくか、西村公利社長の覚悟が問われている。
作家で詩人の佐藤春夫は機上から見た北海道の景色をこう書いている。
《機上から見る北海道は緑と茶褐色との不規則な市松模様の間に、点々と赤い屋根をばらまいた一枚の大じゅうたんである――やがて眼前、眼下のあちらこちらにまるで白墨で書いたような前衛の文字が一面に現れてきた。その難読の文字を読み取ろうと努力したが、「残雪は 山に前衛の 文字を書く」と心中ひとり呟いた》
新生HACは、そんな牧歌的な空のたびを道民に与え続ける使命があるのではないか。