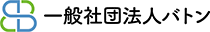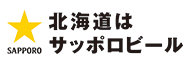ーー笹原さんが、銀行マンとして大切にしてきたことは何でしょうか。
笹原 銀行は、社会的使命を強く帯びた存在なので、公正で誠実であることが求められます。堅い話になってしまいますが、人を偏りなく平等に扱い、私情や利害にとらわれずに物事を判断することが必要です。ルールや倫理に則って行動し、立場や力関係に左右されず、「何が正しいか」で判断する。嘘をつかず、ごまかさず、常に真摯に人や仕事に向き合う。言葉と行動が一致し、自らの言葉に責任を持ち、困難な時も正しいことを選び抜く強さが求められます。
公正で誠実な判断は、信頼の根幹で、組織に健全性と持続性を与えます。公正で誠実な人柄は、周囲に安心感と信頼を与え、お客さまとの関係や銀行の信頼において、その基盤となります。横領や隠ぺいが起きれば、長年積み上げてきた信用は、あっという間に崩れ落ちます。その信頼を回復するのに、どれほどの時間を要することになるのか、それが簡単ではないことは、いくつもの事例が証明しています。私自身はどうかといえば、十分に実践できたとは言えません。一朝一夕で得られるものではないので、私自身、未だ叶わずですが、そうありたいと努めてきたのは事実です。
ーーバブルの前後で、銀行経営の変化やご自身の心持ちの変化はありましたか。
笹原 私は神楽支店で3年3ヵ月勤務した後、事務管理部のシステム部門(現在のシステム部)に配属され、11年ほど在籍しました。当時、預金量が急速に拡大し、CD・ATMや口座振替なども急増していたほか、金融自由化の波が押し寄せる中で、新たな取り扱い業務が増えていたこともあって、大規模なシステム更改が進行していきました。
私はその間、1983年と1991年、1993年の大きなシステム更改にシステム部員として携わりました。従って、バブル前とバブルの進行、バブル破綻直後に経営の近くで業務に関わることはありませんでしたし、営業などを通じてバブル下のお客さまと直接接することもありませんでした。
バブルの期間は、1986年頃から1991年頃までと言われていますが、システム部署にいながらも、時代の異様な変化を感じていました。金利自由化の流れの中で、次から次にさまざまな金利自由化商品が発売され、なおかつ販売しやすくするための販売規制緩和が、半年ごとに繰り返され、頻繁にシステム対応がなされました。
預金や貸し出しの年間伸び率が15%に及ぶ年もあり、お客さまは、少しでも高い金利の商品にシフトしていきました。急増する預金の運用先として、不動産向けや特定先への大口融資を各行が競う状態でした。当行でも東京・青山に店舗が新設され、同期の何人かが配属されましたが、東京3ヵ店や大阪の支店の預金、貸し出しのロットが、道内と比べようもなく大きくて、その金額に驚いたことを記憶しています。各行ともに、遅れてはならないと競うような状況でした。
金融の自由化と国際化が進展し、銀行業務の内容が大きく変化していった時代でもありました。金利自由化に伴って、預貸金利ザヤの縮小が進むのをカバーするため、証券取引や外国為替取引の拡大が重要だという流れがあったと思います。当行も、ニューヨーク支店、ロンドン駐在員事務所、香港駐在員事務所を開設、香港には、外国債券発行のための法人も設置しました。時代背景として、金融自由化、金融業務拡大のタイミングと、バブル経済の進行が同時期に重なったことも傷を大きくした要因の一つと考えられます。新規業務の取り扱いと業容の拡大を競う一方で、過度なリスクテイクを牽制する術を持ち得ていなかったのだと思います。
私が、経営に近い営業企画の部署に異動し、仕事をするようになったのは、1994年以降です。既に、バブルが崩壊し、当行は、藤田頭取の下で不良債権処理を含む合理化計画を進めていました。不良債権処理を進めるには、その原資になる営業利益をしっかりと稼ぐ必要があります。また、信用不安から預金が流出することにも備えて、安定的な資金調達基盤を整えておかなければならない。私は、そうした役割を担う部署のリーダーになりました。
その延長線上で拓銀との合併交渉に入りました。 拓銀との合併委員会では、私は、店舗政策をどうするかという分科会のサブリーダーでした。拓銀側のヘッドは、石井(純二元頭取、元会長)さんでした。統合後の店舗をどうするかを詰めていく分科会でしたが、互いに理解しながらハイペースで進んでいきました。ある意味で統合後の店舗政策は順調でしたが、大元の不良債権については、相当に認識の差があったということは、当時も聞こえていました。