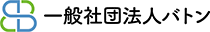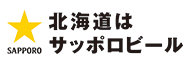国内では国策として、洋上風力発電が進んでいますが、洋上風力はコストが高く、無理して入札に参加すると多額の減損などを余儀なくされます。そうした現下の経験は、将来、絶対にプラスになると思っています。ただ、洋上風力一辺倒ではいけないでしょう。陸上風力発電も大きな電力をつくることができますが、道北では、オジロワシの衝突問題が出るなど、生態系の将来的な姿の中で問題が起きてくるとなると、なかなか思い描くような収益拡大は、できなくなります。一つの方法に偏ると、余計にそういう傾向になり、何か問題が出てくると、全てが止まってしまうことになってしまいます。
北海道には、広い土地があるので、太陽光発電もこれからまだまだ設置が進むでしょうし、水力発電も増えるでしょう。太陽光発電は、技術革新が進んでおり、折り曲げ可能なペロブスカイト型など、まだまだ進化していくと思います。私たちは、北海道国立大学機構のお手伝いもしていますが、帯広畜産大学では、縦型太陽光発電の実証実験も行っています。農業と共生できることが確認できれば、大きく普及していくでしょう。
ーー太陽光発電に関しては、釧路湿原の周囲につくろうという動きもあります。
兼間 そういうところに、許可してはだめだと思う。自然破壊になるようなことでは、元も子もない。利益偏重でものごとを急激に進めようとすると、そういう問題になる。全ては自然との調和、共生を前提に再エネを生み出していくことを考えないと、持続可能な事業にはならない。そこが一番のポイントです。金融機関として、資金を出す時も、そうしたことを審査の中に折り込みながら検証することが、必要になってきます。
もともと、北海道は、エネルギーの供給基地として捉えられてきました。そのため、送電網などの議論になっています。私は、送電網は、日本海側ルート1本で良いと思っています。太平洋側ルートは、見直したら良いのではないか。この議論は、多分これから大きくなってくるでしょう。ワットビット連携の考えが出てきているので、地域のデータセンターの情報を光ケーブルでデータ伝送する方が、送電網を整備するよりもコストは、はるかに安い。ワット・ビット連携の仕組みを活用することが、脱炭素やエネルギーの地産地消に繋がると思います。
ーー本日は、ありがとうございました。