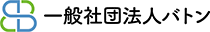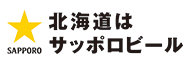ーー以降、ほくほくFG設立への道筋に向かっていきます。
兼間 1999年以降から、貸出金の引き当てに関する議論が深まっていきました。引き当て水準などが固まっていく中で、やはりまだまだ引き当てを積まなければいけない状況になりました。結果から振り返ると、優先株、公的資金がなければ、大変な状況になっていたかもしれないと思っています。
ーー2004年9月に、北陸銀行との経営統合が実現しました。
兼間 北陸銀行は優先株ではなく、一般株の第三者割当増資で、地元からの増資をお願いして、その上で公的資金750億円、公的劣後ローン200億円を導入、両行を合わせると1400億円の公的資金の投入を受けて、ほくほくFGがスタートしました。当時は、弱者連合などと、いろいろなことを言われました。
ーーその後、公的資金は返済しました。
兼間 2009年8月に、ほくほくFGは、公的資金を全額返済しました。そして、2019年から、毎年優先株の10分の1ずつの償還を始めました。これは、バーゼル規制(国際決済銀行=BIS=のバーゼル銀行監督委員会が策定した、国際的に活動する銀行の自己資本比率などの国際的統一基準のこと)が変わり、10年後には、優先株の資本算入が認められなくなるからです。その激変緩和措置として10年間、10分の1ずつ、自己資本に参入する額を減らしていけるようになったので、返済を始めました。
「優先株を早く返せば良いではないか」と、経営統合当初から言われていましたが、私たちとしては、公的資金も返せていない中で、優先株をそれよりも早く償還することは、できないと思っていました。また、公的資金を完済して以降の10年間は、マイナス金利やゼロ金利で銀行収益がどんどん落ちていく時期でした。資本と認められている大事な優先株がなければ、リスクを取ることもできない、という判断もあって、可能な限り、中心的な自己資本として、優先株を使わせていただきたいという方向で進んできました。
しかし、バーゼル規制でそれができなくなったので、これまでに6回償還をして、残額215億円までにきたところで、全額前倒しをしようと決議しました。もちろん、足元の財務内容が、かなり改善してきたこともあります。優先株を全額お返ししても、単体でも8%以上の自己資本を十分確保できるという中での対応です。ようやく、本当の意味での健全化が実現できました。
ーー完済まで、長い道のりでした。
兼間 26年間が経過しましたが、実感としてはあっという間でした。私は、優先株をお願いする前のタイミングから、財務部門で仕事をしていました。1994年に経営企画室に配属になり、1995年2月に経営企画部に組織変更になり、当時の藤田恒郎頭取直轄の経営企画室ができて、そこで仕事をしていました。ですから、正直に言うと、私自身、あまり良い時期を経験したことがありませんでした。不良債権処理など、そういうことばかりをやってきたので、私が言うのも変ですが、“リストラ大魔王”みたいな存在でした。
4年前に頭取に就任してから、経営課題を聞かれた時には、優先株を早期に償還すると言い続けてきました。ようやくそのタイミングまで来たわけですが、だからといって、全てが終わったということではありません。頭取就任時から札幌市内の営業体制を見直したり、道内店舗網の統廃合を行ったり、海外拠点も縮小したりしてきました。人口減少が進む道内において、地域の金融インフラを考えた時、まだまだ検討を進めていかなければなりません。
ーー「道民のATM」の設置台数が増えています。
兼間 昨年7月に、セイコーマートさんへの設置を発表した「道民のATM」は、現在、590台まで設置が完了しています。セイコーマートさんの道内全店舗の半数以上に導入しました。これによって、セイコーマートさんに行くと、各種支払いのほか、送金も自由にできます。給与振り込みをしていただいている方なら、いつ引き出しても手数料はかかりません。通常のATMとして使うことができるので、もっと機能を深めていきたいとセコマさんとも話しています。道内金融機関との連携を深めて、本当の意味で「道民のATM」になれるようにしたい。
道内金融機関のバックヤード業務について言うと、広い道内では、本当に非効率だと思っています。こういったことについては、インフラの共同利用を含めて、引き続き検討していきたい。信金さんとは、現金輸送を共同で行ったりしています。当行のアスビックのような会社は、北洋さんにもありますから、互いに連携してやっていくことだってできるでしょう。また、セコマさんの物流の力を借りながら進めることもできるのではないでしょうか。いずれにしても、さまざまな検討をしたい。流通業界は、物流の効率化が課題ですが、私たち金融の世界でも物流の効率化は今後、検討していかなければならない課題です。