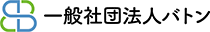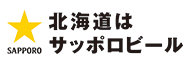(写真は、北海道観光機構正副会長、左から猪又將哲副会長・ファイバーゲート社長、平島誉久代表理事副会長・互信ホールディングス社長、唐神代表理事会長、清水伸一副会長・日本旅行北海道社長、林雅子副会長・JR北海道執行役員開発事業本部長)
(写真は、北海道観光機構正副会長、左から猪又將哲副会長・ファイバーゲート社長、平島誉久代表理事副会長・互信ホールディングス社長、唐神代表理事会長、清水伸一副会長・日本旅行北海道社長、林雅子副会長・JR北海道執行役員開発事業本部長)
もう一つは、北海道観光業界の密度を上げるということです。リーマンショック、東日本大震災、コロナ禍と観光業界は、何度も危機的状況を迎えてきました。北海道は、有珠山の噴火や日本初となるブラックアウトも経験しました。その都度、業界全体で停滞期を迎えましたが、短期間で立ち直り、成長軌道に乗ることを繰り返してきました。大きな目で見れば、安定成長をしてきた産業です。
北海道の総観光消費額は、2019年に1・5兆ありました。コロナ禍で一気に降下しましたが、2024年は1兆5900万円と、前年比125%、2019年比で106%となりました。観光入り込み客数も、2024年は5313万人、前年比106%、2019年比97%まで回復、インバウンドについても2019年比125%まで回復しました。一時、6割まで減少した消費額も入り込み客数、特にインバウンドは、ゼロになったにもかかわらず、4年かけてしっかり回復してきました。この流れを止めず、小金澤会長が掲げた2030年の目標、道内観光消費額3兆円、観光入り込み客数6500万人、道外観光客800万人、インバウンド500万人の達成を必達目標として取り組んでまいりたい。
これからさらに成長を続けると見込んでいる北海道観光業界ではありますが、成長の波に乗るためには、有事の際の危機的状況から立ち直る期間を可能な限り短くして、できれば、ほぼ影響ゼロの状態にしなくてはなりません。そのためには、備え、有事からの回復期に業界を支えるための財源確保が重要です。北海道の観光業界は裾野が広く、他業界に与える影響も大きいということは、2019年から2023年の間に実感として心に残っているかと思います。
他にも、言葉が先行している感はありますが、オーバーツーリズムの問題も、受け入れ側の生活者も含めた地域として、旅行者と共存する仕組みをつくり上げていくことが必要です。インフラの問題も現状、新千歳空港が8割、地方空港が2割という海外からの渡航状態の課題を、地方分散と二次交通整備により解決するなど、地方と地方企業、地方生活者との連携を強化、と申しますか、主体に地方の皆さまにも関わっていただき、地方との密度を上げ、さらには各地方の旅館協会をはじめとする宿泊業界、運輸業界、そして道経連、道商連、道同友会など経済団体としっかり連携し、密度を上げていきます。
さらには、若者を中心に夢のある業界としての認識をしてもらい、多くの優秀な人材が観光業界に集まる人材確保の面も考慮し、人材面でも密度を上げたい。そのための、観光インフラ部会も立ち上げる予定です。多少のアクシデントを跳ねのける、密度の濃い強固なシステムを構築していくことが、北海道経済の一翼を担う私たち観光業界としての使命だとも思っています。
マーケティング戦略は?インフラ問題は?業界の人手不足の対策は?など、具体的な戦略や戦術について、一つひとつ考えを述べるべきとも思いましたが、その前に観光業界に身を置き続けてきた私らしく、リアルな思いと決意、覚悟をお伝えした方が良いと考え、2つの思いをお話させていただきました。
地方観光の推進と発展に注力し、北海道観光業界の密度を上げる。ここまで一企業として観光に従事してきた私だからこそ分かる、感じる当時者として実感を持った私らしい策を行っていき、魅力溢れる北海道の観光業界の構築と北海道経済の発展、道民の笑顔のために貢献したい。