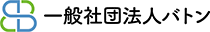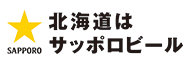食品スーパーは生活に密着した業界だが、ネット社会の台頭や少子高齢化、人口減少によってどう持続可能な体制を構築していくかが問われている。スーパー業界に身を置いてから令和2年で満60年になるアークス(本社・札幌市中央区)の横山清社長(84)は、スーパー業界の変遷を体験してきた今や数少ない現役のトップだ。リアルエコノミーは毎年横山社長へのインタビューで新春を飾っている。今年も横山社長の時代感や自社戦略などをシリーズで掲載する。
アークス・横山清社長新春独占インタビュー①「追い付け、追い越せではない競争時代」
 (写真は、インタビューに答えるアークス・横山清社長)
(写真は、インタビューに答えるアークス・横山清社長)
「昨年は、5月に平成から令和への改元があり、10月には消費税の増税が行われるなど様々なことが巡り来て、まるでミキサーに入っていたような1年間だった。私は、食品スーパーマーケットの業界に入って59年回目の年末年始を迎えた。昭和36年の年末と同37年の年始がスーパー業界に身を置いて最初の年越しだった。今年の年越しは私にとって還暦ということになる」
「セルフサービスのスーパーが全国に広がり始めた昭和33年ころがスーパーの誕生時期とすれば、業界自体は今年で62年ということになり決して若い業界ではない。最初のころは、『スーっと出てパーっと消えるのがスーパー』と揶揄されたこともあったが、今やそういう言葉を知る人も少なくなった」
「昨年の流通業界は、ますます業態の垣根がなくなっていったが、食品のウエートを高めているドラッグストアも医薬品などの粗利の高さを利用した食品の安売りがそろそろ続かなくなるだろう。業態で言えば、ホームセンターも厳しく、コンビニエンスストアも365日、24時間営業という伸びしろの部分を全て使い果たしてその先が見えない状況になっている」
「そんなことを考えると、まさしく昨年は平成の終焉と令和の濫觴(らんしょう=物事のはじまり、起源)がミックスした象徴的な乱気流の期間だったのではないか。潜在化したものはこれからどんどん顕在化する期間に入っていくと思う」
「コトの始まり、物事の起こり、起源のことを濫觴と言うが、面白いと言えば面白く、大変と言えば大変な時代に遭遇することになるだろう。何か具体的にこうだ、売り方がこうなるということではなく相対的な変化に晒されるということだ」
「国内の大手流通2強のうち、1社は全国の数十店舗を閉店すると宣言して実際に閉店を始めている。しかし、もう1社は閉店を宣言したものの閉められない状況だ。建物所有者とキーテナントが自らのグループということもあるからだろう。そうした大変な状況をどこも抱えている」
「アークスグループ9社のそれぞれの設立から現在までの平均年数は60年を少し超えている。会社寿命30年と言われていることを考えるとその倍になるわけだ。つまり、9社は新しい企業でも何でもなく既に老舗の域に入っているのが実態だ。気が付かないうちに時代が変わってしまっており、このままいったら時代遅れになってしまう」
「『変化に対応する』とお題目を唱えてもしようがないが、永遠のリニューアルを続けていかなくてはいけない。もう一回勉強をし直そうと一生懸命に本を読んだりしているが、ペーパーをめくっている学習ではだめだという。今はインターネットですぐ調べられる時代だ。スマホがあれば良いという感覚。このままではネット社会によって人間の感覚も変わってしまうのではないか。そうなると生活様式も変わってくるため、その環境でスーパーという商売の絡みをどう考えていくかだ」
「リアル店舗がなくてもネットであらゆるものが買えて生活ができる時代だが、リアル店舗はなくならないと思う。むしろリアル店舗を持っている企業が生き残っていくと思う。アマゾンがリアル店舗を持つスーパーを買収したり、キャッシュレス無人コンビニのアマゾンゴーで現金が使えるように改装したりしているのは、リアル店舗がカギになると見ているからではないか」
「百貨店の最盛期は市場規模で12兆円(1989年)くらいあったが、今は5兆8000億円になっている。コンビニは現在、11兆円弱の市場規模だが、365日、24時間営業の限界に直面している。食品スーパーの市場規模も13兆円に迫ろうとしているが、やはり12兆円くらいが一つのボーターラインなのかもしれない」
「スーパー業界で言えばメーカー、問屋、商社も含めて生き残れる体制をどういうことでつくっていくかが問われている。他に先んじた企業に追い付け、追い越せでは解決できない競争になるのではないか。人生100年時代と言うが、会社も100年時代だ。毎日、毎日の勉強が必要だが、一つの課題をクリアしても次々と勉強しなければならない課題が出てくる。令和の時代はそういう時代であり、永遠に勉強を継続しなければならない。その中から会社100年時代の戦略を問い続けなければならないということだろう」(次回に続く)