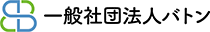北海道の異業種交流組織「一への会」は2025年9月16日、札幌市中央区の京王プラザホテル札幌2階エミネンスホールで、「2025北海道ニューフロンティア経営セミナー」を開催した。今年のテーマは、「北海道のポテンシャルを今こそ活力へ~新たな経営戦略を探る~」。ニトリ(札幌本社・札幌市北区、東京本社・東京都北区)の似鳥昭雄社長に続く2講目は、東京大学大学院農学生命科学研究科の鈴木宣弘特任教授が、『明日の食料・農業・北海道に期待すること』と題して講演した。 (写真は、講演する鈴木宣弘・東大大学院特任教授)
(写真は、講演する鈴木宣弘・東大大学院特任教授)
鈴木氏は、三重県の半農半漁の家に生まれ、現在も自身は農協、漁協の正組合員であり、生産者でもある。鈴木氏は最初に、昨年来のコメ騒動に触れ、「米騒動が、現在も収まらないのは、戦後の占領政策まで遡る。日本は、アメリカの占領政策で主要作物の関税を撤廃、麦、米、大豆、トウモロコシなどの国内生産は壊滅した。それに加えて、GHQは大学教授を支援して、『米を食べると馬鹿になる』という本まで書かせて、当時のベストセラーにもなった。日本が、アメリカの農産物に依存しないと生きていけないような流れをつくっていった。胃袋からの属国化を徹底していった。その後は、関税が回復したものの、米消費が減る流れができ、農業生産が回復してきたら、今度は過剰になって減反政策を取り、それをやりすぎて今回の米騒動に繋がった」と分析した。
現在の食料事情について、経済産業省と農林水産省の覇権争いの影響も受けているとする。「経産省と農水省は、古くから犬猿の仲。経産省は、食糧、農業を生贄にして、自動車で儲ける政策を行ってきた。『食料はいつでも、金を出せば買える。それが、食料安全保障だ』という流れを経産省はつくってきた。その極めつけが、トランプ関税。自動車で脅され、何でも差し出すので許してくれと。絶対に譲ってはいけない最後のカードである日本人の命の要の米を出すから許してくれと。結果、輸入米をどんどん入れていく流れをつくってしまった」と批判した。
「日本は、アメリカから言われたら、戦闘機でも飛行機でも100兆円規模で買わないといけない。緊縮財政だから、どこの予算を削るかというと、標的は農業予算。それがずっと続いてきた。今も続いて、もっとひどくなっている。だから、農業振興の予算が出せない」と農業を取り巻く環境を指摘した。
北海道の食料・農業について、「日本の農業は、世界で一番厳しい競争に晒されながら、今でも世界10位の農業生産額を誇り、正に精鋭の農家。その中でも、一番先頭に立ってリードしてきた北海道は、精鋭中の精鋭の農家。誇りと自信を持って、世界に冠たる循環農業で世界をリードしてきた底力を、今こそ発揮してほしい。私も農家の一人。生産者も頑張るので、ぜひ、消費者、産業、政治行政、協同組合の各分野の人たちが一緒になって農業を発展させていく仕組みづくりを、北海道から広げていってほしい。北海道の力なら、食料・農業の明るい未来を実現できる。一緒に頑張りましょう」と結んだ。