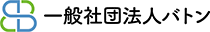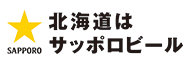エア・ウォーター(本社・大阪市中央区)とエア・ウォーター北海道(同・札幌市中央区)は、2025年5月23日、三笠市と包括連携協定を締結した。2社は、同市と室蘭工業大学が連携して進めている石炭地下ガス化事業の一環として、水素の精製に携わっている。協定締結を機に三笠市が進める水素サプライチェーンの構築に、より広範囲に協力する。 (写真は、エア・ウォーター、エア・ウォーター北海道、三笠市との包括連携協定締結式。左から、エア・ウォーターの松林良祐社長、三笠市の西城賢策市長、エア・ウォーター北海道の庫元達也社長)
(写真は、エア・ウォーター、エア・ウォーター北海道、三笠市との包括連携協定締結式。左から、エア・ウォーターの松林良祐社長、三笠市の西城賢策市長、エア・ウォーター北海道の庫元達也社長)
 (写真は、室工大関係者を含めた記念撮影)
(写真は、室工大関係者を含めた記念撮影)
三笠市は、廃鉱後も7億tが埋蔵されている石炭の有効活用を目的に、室工大と共同で、石炭ガス化事業を2008年から進めている。地下にある石炭を燃やしてガス化したものと、地上で露頭炭と木質バイオチップを燃やして、ガス化したものを混合させて水素を回収する「H-UCG」(ハイブリッド石炭地下ガス化)と呼ばれる事業で、CO2を分離して埋め戻すなどの処理技術も進めている。
エア・ウォーターとエア・ウォーター北海道は、同事業が、2023年にNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の助成事業に採択された頃から参画、発生したガスから水素を精製する技術と、CO2を分離する技術を担当している。助成事業の最終年となる2025年は、奔別炭鉱跡地に石炭と木質チップのガス化装置と水素を精製するユニットを建屋内に設置。砂子炭鉱の地下で発生させたガスをタンクに詰めて、奔別の建屋に搬送、ガスを混合した上で、CO2の分離と30%含まれている水素を精製分離する実証実験(水素発生量は毎時1ノルマル㎥を想定)を10月から1ヵ月間始める。
こうしたブルー水素(CO2排出量を削減した水素)のサプライチェーン構築に前進してきたことから、2社は、市と包括連携協定を締結することにした。市では、得られた水素を市役所の燃料電池向けや道の駅の電源、温泉施設の熱源として地産地消を想定しているほか、CO2に関しては、農業分野への利用も検討している。また、2024年12月に2社がオープンさせたオープンイノベーション施設、エア・ウォーターの森を活用して観光、食、農業、特産品、三笠高校との連携など、さまざまな分野での事業創造も進める。
この日、エア・ウォーターの森で行われた包括連携協定の調印式で、西城賢策・三笠市長は「市は2029年度に水素サプライチェーンの商用化を目指している。少しずつだが体制が整ってきており、今回の協定締結を弾みに実現まで頑張り抜きたい」と話した。エア・ウォーターの松林良祐社長は、「当社は、農業などさまざまな事業をしており、連携を深めて地域社会に役立つ事業を進め、一緒に発展していきたい」と述べた。また、エア・ウォーター北海道の庫元達也社長は、「今まで以上にグループの知的資源を生かしながら、三笠市と共創の取り組みを推進していきたい」と語った。
なお、室工大は、市と2012年に包括連携協定を結んでおり、2018年には、エア・ウォーターとも包括連携協定を結んでいる。今回、エア・ウォーター2社が、市と包括連携協定を結んだことにより、市と室工大、エア・ウォーターグループ3者の協力体制は、H-UCGプロジェクト以外にも広げることができるようになる。