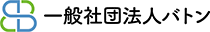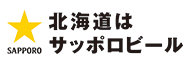ススキノの焼鳥店がひっそりと閉店した。57年間にわたって、歓楽街に集まる人たちの喜怒哀楽を吸い込んできた小さなお店「とり安」。コロナを経てススキノに集まる人の流れが大きく変わり、来店客が減少、店主は閉店を決断した。 (写真は、「とり安」のスタンド看板を前にする織田明さん)
(写真は、「とり安」のスタンド看板を前にする織田明さん)
「とり安」が開店したのは、昭和42年(1967年)2月。現店主、織田明さん(54)の実父が、旧カギヤ会館(南6西4)1階で、3坪の焼鳥店を始めたのが最初だった。実父は同じ場所で営業していた焼鳥店で働いていたそうで、その店を引き継いで「とり安」の暖簾を掲げた。札幌冬季五輪の5年前、ススキノはまだまだ地方都市の歓楽街といった風情だった。
カギヤ会館は、40年ほど前にプラザ6・4ビルに建て替えられ、「とり安」はその1階で営業を続けた。織田さんは中学校を卒業して、その頃から店を手伝い始めた。「父の下について、見よう見まねで焼鳥の作り方を学んだ。焼鳥は焼き方が難しい。炭火の様子と焼き具合を見ながら裏返したり、素材によって焼き時間が違うから、多分に感覚的な技が必要になる」。
当時は、年末年始も休まずに店を開けていたそうで、「スキー客が立ち寄ったり、店はいつもお客でいっぱいだった」(織田さん)。バブル期の賑わいは、織田さんの店にも及び、「鶏肉8㎏、豚バラの半身2枚を1日で使い切っていたし、父親は1日中、串刺しを続けていた」(同)。
2005年に今の店(南7西5)に移ってきた。ススキノの外れにあたり、ソープなどが軒を寄せる場所だが、40代から60代のサラリーマンを中心に、名物の半身焼きを求めるお客で順調な商売を続けてきた。2011年に実父が死去、織田さんは店主として店を継いだ。
一変したのは、2020年から始まったコロナ禍から。店を開けられず呻吟する日々。ようやく店を再開しても、客足は以前ほどに戻らない。コロナが明け、ススキノの人流は大きく変わった。地元のサラリーマン層はススキノに足が向かわず、目につくのは若者と観光客ばかり。「このまま続けても仕方がないと思うようになったのは2年ほど前から。それでも、親父が始めた店を閉めることには抵抗があった。なかなか踏み切れなかったが、ズルズル続けていてもお客さまに失礼だと考え、今年2月に閉店を決断した」と織田さん。
カギヤ会館の時代から通ってくれたお客や2代続けての常連客たちからは「寂しくなる」と言われたが、時代の流れと割り切った。「ススキノは、コロナを経て変わってしまった。57年のうち、私は40年ほどこの店に携わってきた。寂しくないといえば嘘になるが、未練はない」。織田さんは飲食業にはもう戻らないという。「次の仕事をゆっくりと探すよ」とひとりごちた。